
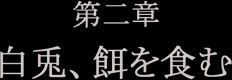

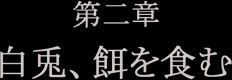
『美女たちのランキングバトル』 収録から三日後の夜、その日最後の仕事となった、新宿でのロケを終えた真紀は、マネージャーの安川が運転する車で、都内某所の、真紀の所属する事務所へと向かっていた。
真紀は、安川に、「仕事のことで会わせたいお客さんが来るので、社長が、仕事が終わったあとに事務所に寄って欲しいと言っている。」
としか伝えられていなかった。真紀は、その来客が、どういう人物なのかを、何度か安川に尋ねてみたが、返って来る答えは、「いやぁ、僕も聞かされてないんですよ。」
というものだけだった。
やがて、車は、事務所のすぐ脇に止まった。運転席から降りた安川は、携帯電話を取り出して、短い通話を行ったあと、真紀のために、後部座席のドアを開けた。
「お疲れ様でした。例のお客さんは、もう見えているので、直接応接室に来てくださいとのことです。……
それでは、僕は一旦失礼して、軽く食事してきますね。」
「あれ? 安川さんは、そのお客さんには会わないんですか?」
「ええ。ちょっと外してくれ、って言われてるんですよ。…… 何か、ワケアリみたいな感じだし、とりあえず今のところは、首を突っ込まないでおきます。」
「ああ、そうなんですか。……」
「真紀ちゃんを事務所に戻してくれって連絡を、社長から初めに受けたときに、真紀ちゃんの、来月後半のスケジュールも訊かれましたから、そのあたりに何かあるんじゃないですかね。……
お話は、二、三十分で終わる、ってことでしたので、その時間ぐらいには事務所に戻ります。そしたら、お家まで送りますんで。」
「はい。わかりました。行ってらっしゃい。」
真紀が事務所に着き、応接室のドアをノックしてから開けると、そこには、社長の他にもう一人、先客がいた。
少し白いものが混じった長めの髪、同じ色合いの上品に手入れされた口髭、今ではあまり見かけない大きめのレンズを使った縁なし眼鏡、……
業界人という基準で考えるとやや地味目のジャケットを羽織り、来客用のソファに腰を下ろしている、見たところ四十代後半ぐらいのその男性は、応接室に入ってきた真紀に、軽く会釈をした。
「あら、坂田さん。…… おはようございます。」
真紀に、坂田と呼ばれた男は、笑顔で真紀に挨拶を返し、社長の隣の一人用ソファにかけるよう、真紀を促した。
「坂田さんが来てるってことは、…… 今度は泥レスでもやらされるのかな?」
ちょっと意地悪そうな笑顔で真紀がそう言うと、坂田は、「こりゃまた強烈な先制パンチだね。」
と洩らし、力なく笑った。
真紀が、坂田と顔を合わせるのは、これが三度目になる。
真紀が坂田に初めて出会ったのは、二年ほど前。真紀が、あまりテレビの仕事と縁がなかった、まだそれほど売れていない頃、坂田は、深夜枠ではあるものの、真紀に全国ネットのテレビ番組の仕事を持ってきた。
グラビアアイドルとキャバクラのホステスを何人かつづ集め、それぞれをチームにして、ヤラセなしの真剣ファイト、そして、負けたら顔面パイの罰ゲーム。……
もちろん真紀は、この仕事を、屈辱的な仕事だと思っていたし、今でもその想いは変わっていない。
しかし、当時の真紀にとっては、貴重な全国ネットの仕事であり、弾けたキャラの等身大像を初めて世間に広く露出することで、今の、超売れっ子の地位を築き上げるきっかけになった仕事として、真紀はこの仕事をありがたくも思っていた。事実、この深夜番組に出ることによって、星野真紀はブレイクしたと確信しているマニアックなファンも多い。
真紀を、ボクシングの魅力に引きずり込むきっかけを作ったのも、また坂田だった。『アイドル・ボクシング・スタジアム』
の企画案が詰めの段階に入っているころ、企画チームの一人に、「この企画なら、一発目の収録に、まず星野真紀を確保したい。彼女なら、必ず素晴らしいパフォーマンスを披露してくれるはずだ。」
と、坂田はアドバイスを与えていた。
真紀が、『アイドル・ボクシング・スタジアム』 への出演を受けた折に、坂田が真紀の事務所に挨拶に訪れたのが、真紀と坂田の二度目の出会いだった。その際、坂田は、「もし、収録前に少しでも練習しておきたいなら」
と、現在、真紀が足繁く通い詰めているボクシングジムを、真紀に紹介していた。
坂田と自分との接点を、真紀は、これ以外には思いつかなかった。そんなこともあり、真紀の頭の中には、『坂田=ファイトの仕事を持ってくる、ちょっと怪しいおじさん』
という図式が、すでに出来上がっていた。
真紀が椅子に腰を下ろすと、隣の席に座っていた社長が、真紀に話しかけてきた。
「今日、事務所に戻ってもらったのは、坂田くんが、ちょっと毛色の変わった仕事を真紀ちゃんに持ってきたからなんだけどね。……
僕は、もう、坂田君から大まかな内容を聞いてて、事務所としては断るつもりでいるんだが、坂田君の方は坂田君の方で事情があるみたいでね。まあ、話だけでも聞いてやってくれないかな。」
「はい。…… でも、…… 安川さんに外してもらった、というのは、何か理由が?」
「うん。内容が少しばかりハードなもんだからね。…… 彼が同席すると、坂田君もしゃべりにくかろうと思ったんで、安川君には、遠慮してもらった。」
マネージャーを同席させないことを、多少不思議に思ったが、社長の指示でもあることなので、真紀は、「わかりました。」
と返事をした。すると、社長は、坂田に、話を始めるよう促した。
「じゃ、早速始めさせてもらうよ。…… 実は、ある人物に、女の子同士のボクシングを見せる場をコーディネイトするよう頼まれてね。で、その場で、真紀ちゃんに、ファイターとしてリングに上がってもらいたい。……
手っ取り早く言うと、そういうことなんだけどね。」
「やっぱりファイトのお仕事なんですね。」
そう言うと、真紀は、くすくすっと笑った。
「まぁ、そうなんだが、…… 実のところ、真紀ちゃんが最近、テレビでやってるようなものとは、かなり質、って言うかな、……
テイストが違うんだよね。」
「…… テイスト、…… ですか?」
「うん。…… 僕がこれまでに真紀ちゃんにお願いしたのは、どっちもテレビのお仕事だったけど、今日、僕が持ってきたのは、ある意味それとは対極の、限られた少数の人たちだけに見てもらうような、そういう類のものなんだよね。……
会場は、都内のナイトクラブを使うんだけど、当日はそこを借り切る形で、僕、それから僕の依頼人に当たる人物、それと、クラブ側が招待した、限られたお客さんしか入場できないような、そんな環境で行われるんだ。」
「ふーん。…… 何か、秘密のパーティーみたいですね。」
「そう。雰囲気はそんな感じだね。…… で、…… 実はねぇ、…… 先に白状しちゃうと、僕個人としては、今回の仕事を真紀ちゃんに請けてもらえる可能性は、限りなくゼロだと思ってる。」
「あら、…… そうなんですか?」
「うん。…… じゃぁ、それにもかかわらず、何でこうやって、真紀ちゃんのとこまで、わざわざ足を運んだか、って言うと、さっき、社長も触れたように、僕の方に、ちょっとした理由があってね。」
「あ、…… はい。……」
「まあ、そこらへんは後で説明するんで、仕事を請ける、請けないということではなく、今のところは、ただの世間話、と言うか、ああ、こんな世界もあるんだ、ぐらいの、軽い気持ちで聞いてもらえばいい。……
いいかな?」
真紀は、坂田がかなり下手に出てきたのを、少し不審に思った。しかし、この仕事の話をちゃんと聞くことで、坂田の顔を立てることになりそうだし、もしかすると、何か面白い話が聞けるかも知れない、とも、真紀は思った。
真紀は、「わかりました。」 と坂田に告げ、にっこりと微笑んだ。
「じゃあ、まず始めに、僕が一体どんな人物なのか、どんな仕事をして、日々の糧を得ているのか、ということをお話しておくことにしよう。……
昔は、フリーの企画屋みたいな感じで、芸能関係のいろんなことに手を出していて、その頃から、社長とは、細々とではあるけれど、お付き合いをさせていただいてるわけなんだけど。……
で、十年ぐらい前から、女の子同士のファイトに関する仕事が少しずつ多くなってきて、今はほとんどそれ専門になっちゃってる。まぁ、この辺りは、真紀ちゃんもうすうす気がついてるんじゃないかな?」
坂田がそこで一旦話を止めると、真紀は、表情を崩し、首を二度ほど縦に振った。
「で、僕が、今までに、真紀ちゃんにお願いした仕事は、どっちもテレビのお仕事だったわけだけど、実のところ、テレビのようなマスメディアがらみのものは、僕の仕事としては、むしろ少数派でね。……
」
「あ、そうなんですか?」
「うん。テレビって、女の子同士のファイトっていう需要自体が、それほどあるわけじゃないからね。だから、それだけで飯を食っていく、というわけにはいかない。……
僕が主戦場としているのは、それとは対極の、濃厚なファイト、…… 別な言い方をすると、女の子同士のファイトを、上質なエロスの対象として捉えているような、マニアックなお客さんだけを対象にしたものなんだよね。」
「上質なエロスの対象、…… ですか?」
「例えば、レスリング系のものであれば、負けたらコスチュームを脱がされてしまうような、いわゆる
『コス剥ぎマッチ』 と呼ばれるものであるとか、初めから裸、もしくはそれに近い形で闘ってもらうとか、……
早い話が、いろんな形で、リングに上がる女の子の裸を見せるわけだ。ボクシングの場合は、トップレス、つまり、上半身裸の状態で、女の子に試合をしてもらうのが基本だね。」
「えーっ! …… それって、…… おっぱい丸出しで、ってことですよね。」
「そういうことだね。…… まぁ、真紀ちゃんみたいな女の子の立場からすると、こう、男の薄汚れた欲望みたいなものを利用して商売してるように見えるだろうから、僕のような人間には、あまりいい印象は持ってくれないとは思うけどね。」
「…… ああ、…… いえ、…… 正直なところ、私にしても、この、胸の谷間を一番の武器にして、芸能界で生きているわけですから、……
そういう意味では、坂田さんと同じかも知れません。あまり大きなことは言えないですね。」
そう言うと、真紀は、力なく微笑み、少し上目遣いの視線を坂田に向けた。
「そう言ってもらえると、僕としても救われる。…… そんなことで、今言った、マニアックなお客さんの、欲求なり妄想なりを満たす場をコーディネイトすることで得られる報酬が、今のところ、僕にとっては、主な収入源になってる、ってことなんだね。……
で、今回も、ある人物からの依頼を受けて、こうして真紀ちゃんのところに足を運んでるんだけど、……
今度の仕事は、僕にとっても、ちょっと特別でね。」
「ちょっと特別?」
「うん。…… 今回の、『女の子ボクシング観賞パーティー』 は、ある人物が、商売上のお客さんを接待するために、僕にセッティングを依頼してきたものでね。で、この、接待される側のお客さん、っていうのは外国人で、来月の後半あたりに来日することになってるんだけど、僕に仕事を依頼した、接待する側の人間としては、どうしても、その接待を成功させたい事情があるらしくて、経費のことは考えなくていいから、とにかく上質のものを、っていう注文なんだ。……
というわけで、お金をふんだんに使える、っていう環境が出来上がったんで、僕としても、その期待に応えるべく、一発豪華なものを、と思ってるんだよね。」
坂田の、『一発豪華なもの』 という表現に、真紀は、激しく好奇心をかきたてられた。
「ねぇ、坂田さん、…… 今、坂田さんが言われた、上質、とか、豪華な、っていうのは、具体的には、どういうことなんですか?」
「あー、それはね、やっぱり、ファイターとして、いい女の子を揃える、ってことが、何と言っても一番だね。……
こういうファイトは、競技ではなくて、あくまでもショー、…… と言うか、より近い表現をすると、『見世物』
なわけで、見る側にしてみれば、リングに上がる女の子が、ボクサーとして、競技者としての技量が高いことよりも、美人であったり、ナイスバディであったりすることの方が、何倍も重要なわけだ。」
「あー、なるほど。」
「しかしながら、ボクシングの場合は、目の肥えた、マニアックなお客さんを、本当に満足させるようなレベルの女の子を見つけるのは、結構大変だ。グローブをつけているとは言え、所詮は殴り合いだからね。特に、顔を殴られる、っていうのは、とりわけ美人の女の子にとっては、どうしても敬遠したいはずだ。」
「んー、確かにそうかも知れないですね。…… でも、ヘッドギアをしてれば、ある程度だったら平気じゃありませんか?」
「いや、ヘッドギアはなしだ。リングに上がる女の子には、マウスピースを除く防具を一切しないで、試合をしてもらってる。」
「えっ? ヘッドギアなしですか?」
「うん。ヘッドギアをつけると、どうしたって、一部であれ、顔が隠れちゃうだろう? 顔とか髪とかって言うのは、その女の子が魅力的であることの、一番のアピールポイントだから、これはちゃんとお客さんに見せる必要がある。それは何故かと言うと、さっきちょっと触れたように、これが競技ではなく、見世物だからなんだね。……
同じ理由で、女の子のボディラインをそのまま見てもらうために、胸や下腹部の防具もなしなんだ。」
「ああ、…… それだと、女の子にとっては、かなり厳しいですねぇ。……」
「それに加えて、上半身は裸になってもらうわけだからね。…… ああ、いいタイミングだから、ボクサーとして、リングに上がる女の子の、リングコスチュームについても、ちゃんと説明しておこう。身に着けるのは、かなり短い丈のトランクスと、その下に穿くアンダーウエア、それと、シューズ。あとは、道具としてボクシンググローブとマウスピース、これだけだ。これでイメージできるかな?」
真紀は、少し考える素振りをしてから、首を縦に振った。
「うん。…… じゃ、話を、上質とか、豪華とかいうことに戻そう。今回の場合はお金が使える状況なんで、そういう格好でリングに上がってくれる、美人でナイスバディの女の子を、言い方は悪いけど、お金で集める。これが豪華さの最たる部分だね。……
あとは、…… どういう器を用意するか、ってことになるのかな。外部の目が完全にシャットアウトできて、雰囲気に品があって、居心地が良くて、美味い酒が出せて、……
まぁ、これに関しては絶好の条件の店がある。都合のいいことに、そこで店長をやってる男が、僕とちょっとした知り合いなんで、その夜は、その店を借り切れるように、もう話は通してあるんだけどね。」
「それじゃ、今度僕が依頼を受けた、『女の子ボクシング観賞パーティー』 の、全体的な流れみたいなものも、少し話しておくことにしよう。試合は全部で五つぐらい組むことになると思うけど、その場合は、始めの四試合を、前座のような形で進める。……
で、最後の試合が、その夜のメインイベントだ。…… もし、真紀ちゃんが出てくれるなら、もちろんメインイベンターに、ってことで、僕としては考えてるんだけど、……
これは、前座として行われる試合とは、ちょっと違った提供方法をしようと思ってる。」
「違った提供方法 ……?」
「…… まぁ、そのへんは、この先の話を聞いてもらえばわかるだろう。…… まず、前座扱いの試合だけど、これはまぁ、女の子にトップレスになってもらって、普通にボクシングの試合をする。……
普通とは言っても、『コス剥ぎマッチ』 の形式は取るから、KOされた女の子は、リングの上でトランクスとアンダーウエアを脱がされる、っていうことになる。」
「うわぁ、それって全裸ですよね。…… あ、でも、KOされた、ってことは、判定とか、引き分けとかのときは、その、……
コス剥ぎは、ナシってことですよね?」
「厳密に言えばそうなるだろうけど、…… まぁ、そのへんは、女の子の方でうまくやってくれるだろう。」
「え? うまくやるって、…… 真剣勝負じゃない、ってことですか?」
「いや、真剣勝負は真剣勝負なんだけど、ある程度、勝ち負けが見えた段階に入ったら、その時点から、不自然さを感じさせない、魅力的なKO劇で終わるように、女の子に勝ち役と負け役を演じてもらう、ってことになるね。」
「…… それは、…… どうしてですか?」
「それはね、…… 判定で何となく試合が終わっちゃうのと、きっちりKOで試合が決まって、コス剥ぎの儀式まで見ることができるのと、お客さんはどちらの結末を望むか、ってことだね。その答えは、……
もちろん、真紀ちゃんにもわかるよね?」
「あ、なるほどー。そういうことだったんですね。」
「うん。…… その他にも、リングに上がる女の子には、いろいろ指導してある。例えば、同じKOで終わるにしても、負ける側は、寝転がるでも、へたり込むでもいいから、ちゃんとダウンした状態でカウントアウトされるようにしなさいとかね。レフェリーストップみたいな形で試合が終わるより、ダウンした選手がテンカウントを受ける方が、見た目的に魅力的な終わり方だし、実は、自然な形でコス剥ぎに移るためにも必要だったりするからね。」
「あ、確かにそうですね。」
「それと、防具をつけないとは言え、やっぱりケガはしてもらいたくないから、安全面にもかなり気を使ってる。頭同士をぶつけて顔に傷がつかないように注意するとか、いいパンチをもらったら、とりあえずダウンして、相手の攻撃から隔離された状態を作るとか、……
これは、ダウンシーンを見せるということに加えて、ダウンした女の子が、本当に試合を続けても大丈夫か、ということを、レフェリーに確認させる機会を与えるという意味でも、とても重要なんだよね。
」
「へぇー。…… 何か、結構奥が深いんですね。」
「まぁ、そうなのかも知れないねぇ。…… で、試合の様子はビデオに撮って、あとできっちり査定をするんだ。試合全体の流れや、盛り上がり加減、KOシーン、ダウンシーンの見栄えの良さ、それから、お互いに無駄なケガをしないように、安全面にどれだけ配慮できていたか、……
この辺りを充分吟味して、ギャラ以外に、ボーナスという形で反映させている。そうすることで、女の子も頑張ってもくれるから、僕としても、よりレベルの高いものをお客さんに提供できる、ってことだ。」
真紀は、坂田の説明に何度も頷いた。なかなかしっかりとしたシステムだ。ビジネスとしてやっていくには、このくらいの配慮をしないといけないのだろう。……
と真紀は思った。
「話が横道にずれてしまったね。じゃ、前座の話はここまでにして、メインイベントの話に移ろう。……
前座格の試合に関しては、肌の露出、という部分が、ウリとしてのかなり大部分を占めちゃってるわけだけど、メインイベントは、試合そのものに関しては、肌の露出は多少押さえ気味、……
トップレスではなく、スポーツブラみたいなものをしてもらおうかな、と思ってる。で、最終的に、勝者と敗者の落差みたいなものを最大限に引き出す、ということを一番のウリにしようかな、と。……」
「…… 勝者と敗者の落差、……」
「うん。…… 勝負がついたら、敗者にとって最も屈辱的な、僕らの世界で、『DS』
と呼ばれている罰ゲームをしようと思ってる。」
「DS、…… 何かの頭文字ですかね?」
「DはDominator、…… 女性形だとDominatrix になるけど、…… 支配する者、という意味だね。で、SはSlave、こっちは奴隷だ。……
つまり、敗者が勝者の奴隷になる、…… ちょっと言い方を変えると、勝った子は、気が済むまで、負けた子を苛めていい、ってことなんだね。……
勝った子は、相手にケガをさせるようなものでなければ、負けた子をどんなに邪険に扱ってもいいし、負けた子は、それがどんな屈辱的なものであっても、勝った子に命令されたら、それに従わなければならない。……
例えば、勝った子が、股を開けと言ったら、負けた子は股を開かなければいけないし、靴を舐めろと言ったら、負けた子はそれに従わなければならない。……
そんな感じだね。」
「うわぁ、…… それはまた、…… 強烈ですね。……」
「うん。…… この夜のお客さんは上客だけだし、部外者の目が入り込む心配もないから、フィナーレとしては、このくらい過激なものを用意しないとね。」
「まあ、こんなとこかな。…… じゃあ、あとは、質問タイムにしようか。真紀ちゃん、何か訊いておきたいことはあるかな?」
「うーんと、……」
真紀は、あごに人差し指を当てて、しばらく考えていたが、やがて、何かを思い出したように、坂田に視線を向け、「坂田さんが、真紀のところにこのお話を持ってきたのは、どうしてですか?」
と尋ねてきた。
「ああ、それはね、依頼人のリクエストなんだよね。…… さっきも話したように、僕の依頼人にしてみれば、この接待を、何としても成功させたいわけだ。だから、女の子同士のボクシングをやるにしても、どんな女の子をリングに上げれば、そのお客さんの満足度が上がるのか、ってことについて、いろいろ探りを入れたみたいなんだね。……
そこで、真紀ちゃんの名前が、真っ先に、そのお客さんの口から出た、ってことらしい。」
「ってことは、その、外国人のお客さんが、真紀がボクシングするところをナマで見てみたい、って言ったんですね。」
「多分、そういうことだろうね。で、僕の依頼人にしても、真紀ちゃんをそういう場に持ち出すのは、極めて難しいってのはわかってるんだけど、それを百も承知の上で、断られたら断られたで構わないから、とりあえず、当たるだけは当たってみてくれ、ってことだったんで、僕がこうして、真紀ちゃんに話を持ち込んだわけなんだ。」
「ふーん。…… ねぇ、坂田さん。私はともかく、こういう、えっちな格好でボクシングしてくれるような女の子って、簡単に集まるものなんですか?」
「んー、微妙なとこかな。…… さっきも言った通り、このパーティーでは、前座に当たる試合を四つほどやって、最後に、目玉になるような対戦者同士の組み合わせによるメインイベント、っていうことになるんだけど、……
前座格の試合に出てもらう女の子の宛ては、まぁ、僕もこういう仕事は長いから、いくらでもあるんだよね。ただ、メインイベントとなる試合に出てもらう女の子、となるとね。顔やスタイルだけでなく、どうしてもネームバリューが欲しいから、ちょっと難航するかも知れない。……
依頼人から、メインイベントに出てもらいたい芸能人のリストを預かってて、その人たちに話を持ち込んでる最中なんだけど、その中に入ってる、かなりのネームバリューを持ってるタレントさんが、一人だけ、条件次第では考えてもいい、って言ってくれてはいる。」
「ええっ? それ、誰ですか?」
「聞きたい? …… よねぇ、やっぱり。」
真紀は、自慢の大きな胸を少し突き出した、おねだりポーズを取って、涎を垂らさんばかりの、物欲しそうな笑顔で、縦に首を振った。
「他の人には、ナイショにしといてよね。…… メイリンだよ。」
「メイリン?!」
坂田の口から、メイリンの名前が出ると、それまで穏やかだった真紀の表情ががらりと変わった。
しばらくの間、黙ったまま、目の前のテーブルの上に視線を落としていた真紀の頭の中では、いくつもの妄想が渦を巻いていた。そして、それが、『リングの上でメイリンを打ち負かし、生き恥を晒させる』
という形にまとまった瞬間、真紀は再び顔を上げ、厳しい眼差しで、坂田を見据えた。
「メイリンが相手なら、…… 私、…… 受けてもいいです。…… 坂田さん、もっと詳しい話を教えていただけませんか?」
「どうしたの、真紀ちゃん。…… メイリンと何かあったのかい?」
「…… 隠しておいてもしょうがないから、お話ししますけど、…… このところ、何度か、メイリンとバラエティ番組の収録で一緒になることがあったんですけど、あの人、何かと私に突っかかってくるんです。……
あの人は、ああいうキャラだし、私の思い過ごしかも知れないんですけど、……
でも、私には、メイリンが私に悪意を持っているとしか思えない。…… 最近は、ジムで練習しているときも、メイリンの顔を思い浮かべて、思いっきりサンドバッグを叩いたりしてますし、……」
「…… なるほどねぇ。そんな事情があるんだ。…… でも、今まで説明してきた通り、今度の仕事は、生半可なものじゃないよ。それでもいいのかい?」
「もちろんわかってます。…… でも、あの人を堂々と殴れるチャンスなんて、そうそうあるもんじゃないですから。……」
「わかった。…… それじゃぁ、真紀ちゃんがメイリンと試合をするなら、どういう条件になるのか。……
真紀ちゃんにしても、メイリンにしても、かなりの売れっ子アイドルだから、当然メインイベンターとして、リングに上がってもらうことになる。それを前提として、話を進めていくことにしよう。」
「はい。お願いします。」
「まず、前座格の試合では、試合の終わり間際に多少演技が入ったりするけど、メインイベントは完全なガチンコだ。……
試合のルールは、一般的なボクシングのルールと同じ。ただし、一ラウンド三分のラウンド無制限で、テンカウントのKOのみで勝敗を決める形になる。それから、シューズ以外のリングコスチュームは、こっちで用意したものを使ってもらう、と。……
で、罰ゲームは、さっき僕が話した通り、真紀ちゃんが勝ったら、そのあと、真紀ちゃんがメイリンを奴隷扱いできる、という形にする。でも、万が一にも試合の結果が逆だったら、罰ゲームの立場も逆になるんだよ。いいね。」
「ええ。わかってます。」
真紀の返事を聞いて、坂田が説明を続けようとすると、真紀は、「あのぅ ……」
と口に出した。
「…… さっき、坂田さんは、部外者を完全にシャットアウトできる環境、っておっしゃいましたけど、……
私がそういう試合をすることを、本当に、世間の目から内緒にできるんでしょうか。……」
「うん、真紀ちゃんにとっては、それが一番気がかりだろうね。…… その点に関しては、心配しなくて大丈夫だ。こういう、過激で、えっちな風味の強いイベントってのは、口の堅い、秘密が守れるお客さんだけを対象にすることで、存続していける。情報を洩らしたことが発覚して、次からそういうイベントに呼んでもらえなくなることが、彼らにとっては一番痛手なんだよね。……
当日、会場となる店に来るお客さんの数は、僕が直接声を掛ける人が四十人ぐらい。それに、会場となるお店の方でも、そういうイベントが好きそうないいお客さんを集めるようなんで、全部で、その倍ぐらいになるんじゃないかな。でも、どちらも信頼できるお客さんだと思ってもらっていい。」
「…… その、…… お店、っていうのは、どんなところなんですか?」
「んー、名前を聞いただけじゃわかんないと思うけど、六本木にある、『プライムローズ』
っていう店だよ。あそこのお客さんなら確実だ。ボクシングだけじゃないけど、同じようなファイト系のイベントの器として、前に何度か使わせてもらってる。もちろん、そのときも問題はなかったからね。」
「プライムローズ、…… あ、それって、もしかすると、彩さんのお店じゃないですか?」
「ああ、そうだよ。…… 良く知ってるね。」
「ええ。…… 前に一度、…… あのお店で、彩さんがバースデーパーティーをしたときに、ご招待をいただいたことがあるんです。……
そのときに、どんなお店で、どんなお客さんが来るのかも、彩さんから聞いたことがありますし。……
確かに、あそこなら、外部の目を遮断するという点では、心配なさそうですね。」
このあと、坂田は、試合に出ることのギャラ、言わばファイトマネーとして、真紀を四日ほど拘束できる程度の額を、そして、試合に勝ったら、勝利者賞として、ちょっとした高級車が買えるほどの額を用意する、と説明した。
この勝利者賞は、確かに魅力的な金額ではあったが、真紀にとって、お金の話は、むしろどうでも良かった。ボクシングの試合という、まったく遠慮をする必要のない場で、メイリンを思い切り殴ること、そして、試合の勝者となり、大勢のお客さんの前で、メイリンを奴隷扱いすること、それ自体が、自分にとっての、最高の報酬だ、と真紀は思った。
坂田が一通り話を終えた時点で、真紀の腹は固まっていた。あとは、社長が首を縦に振ってくれるかどうか。……
真紀は、この打ち合わせが始まってからずっと、坂田と真紀とのやりとりを黙って聞いていた社長の顔を、真剣な顔で見据えた。
「坂田、もう日取りは決まってるのか?」
「ああ。来月の二十二日。一応、まだ予定という形ではあるが、まず変更になることはないだろう。……
真紀ちゃんには、当日、午後七時ぐらいまでに、店に入ってもらうぐらいの感じで、時間を空けてもらえばいい。送り迎えの車はこっちで用意する。」
社長は、「そうか。……」 と言ったきり、再び黙って何かを考えている様子だった。そして、真紀の顔の方に視線を向けた。
「真紀ちゃん、本当にやりたいのかい?」
真紀は、真剣な表情をピクリとも変えず、社長の目をまっすぐに見据えたまま、無言で大きく頷いた。
「うむ。…… そこまで言うなら、真紀ちゃんのやりたいようにさせてあげようか。……
もし、その試合とやらが本決まりになったら、その日の午後以降を、その試合用、それから翌日と翌々日を、試合後の休養に充てる、とそんな感じに、正味二日半分のスケジュールを調整するよう、安川君に伝えておこう。それから、ギャラは一応事務所で預かるけど、勝利者賞としてもらった賞金は、そのまま懐に納めてもらっていい。これでいいかな?」
真紀は、「はい。…… ありがとうございます。」 と返事をし、社長に向かって、小さく頭を下げた。普段、人に頼みごとをしたときには、満面の笑みで感謝の気持ちを伝える真紀だったが、このときは、思いつめたような、真剣そのものの、真紀の表情が変わることはなかった。
「それじゃ、今言った通りの条件で試合に応じるかどうか、さっそくメイリンの方に話をしてみる。OKが取れたら契約は成立だ。……
真紀ちゃん、そうなったら、もう、『やっぱりやめます』 は聞けないよ。いいね。」
椅子から腰を上げた坂田がそう念を押すと、真紀も椅子から立ち上がって坂田に一歩近づき、射るような視線で、坂田を見つめた。
「ええ。…… 坂田さんこそ、…… メイリンを逃がさないでくださいね。」
坂田が真紀の事務所を離れてから少しすると、マネージャーの安川が事務所に戻ってきた。安川は社長に挨拶をしたあと、事務所のすぐそばに停めてあった車に真紀を乗せ、真紀の自宅に向けて、車をスタートさせた。すると、後部座席に座っていた真紀が、運転席の方へと身を乗り出してきた。
「安川さん。…… うちじゃなく、ジムへ行ってもらえない?」
「えっ? それはかまいませんが、…… でも、この時間だと、着いて二十分もしたら、ジム閉まっちゃいますよ。」
「いいの。…… とにかく、三分でも五分でも、…… どんな短い時間でもいいから、今から、サンドバッグを叩いておきたいの。だから、ジムへ向かってください。」
真紀の勢いに押され、安川は、「わかりました。」 と真紀に告げて、車の目的地を変更させた。
翌日、真紀の元に、メイリンが試合の話を承諾した、との連絡が入った。この日から、真紀は、タイトなスケジュールの合間を縫って、それまで以上に、ジムで過ごす時間が多くなった。また、テレビ局の控え室で、他の出演者から離れて収録待ちをしているときにも、シャドーボクシングをしながら身体を動かしている真紀の姿を、安川は、頻繁に目にするようになった。
不思議なことに、真紀とメイリンとの試合が決まってから、二人が同じ番組の収録で顔を合わせることは、まったくと言っていいほどなくなった。
試合の二週間ほど前、真紀とメイリンは、お互いのマネージャーを同伴する形で、某テレビ局内の廊下ですれ違った。その際、二人はお互いに軽く会釈を交わしたが、その別れ際に、お互いの視線が切れようとした瞬間、二人の口元に浮かんだ、殺し屋のような冷たい笑みを目撃した安川は、背筋が凍るような感覚を覚えたという。