

『最後の試合』と決めて臨んだ絵里子との対戦のあと、麗子は、じっくりと時間をかけて、数学教師としての復職先を探していたが、理保が夏美を破って新人王となったのを見届けたのと同じ頃、麗子は、恩師に当たる人物から、「私が理事長をしている学校で教鞭を取ってもらえないか」という招きを受けた。麗子は、その人物を深く尊敬していたし、環境的にも申し分ないものであったので、麗子は彼女の招きに応じることにした。
数学教師に戻ったら、ボクシングからは完全に身を引く。…… 麗子は以前からそう決めていたが、ボクシングから離れる前に、自宅にあるプライベートジムで、理保や夏美と、一度、試合に近い形でスパーを行い、二人の実力を確かめておきたい、とも考えていた。麗子がその話を理保に伝えると、理保は、「ぜひお願いします。」と答えた。さらに理保は、夏美と連絡を取り、麗子の新しい教師生活がスタートするひと月ほど前に当たる、二月の終わり頃にスケジュールを合わせた。
麗子は現役を引退しているものの、理保や夏美よりも体重が二階級上であったし、実力という面から見ても、まだ二人よりも数段上だったので、この試合形式のスパーは、麗子がいくらかのハンディキャップを負うことにした。最終的に、実際の試合と同じ、一ラウンド三分のインターバル一分で、理保と夏美は、一ラウンドごとに交代。完全な真剣勝負で、三人のうち、誰かが、「参った」と言ったら試合終了、ということになった。

![]() 恐らく最初で最後になるであろう麗子との真剣勝負に想いを馳せながら、理保と夏美がサンドバッグを相手に、ウォーミングアップをしていると、およそ一年ぶりに、試合用のトランクス、シューズ、ボクシンググローブを身につけた麗子が、シャドーボクシングを切り上げ、二人に近づいてきた。
恐らく最初で最後になるであろう麗子との真剣勝負に想いを馳せながら、理保と夏美がサンドバッグを相手に、ウォーミングアップをしていると、およそ一年ぶりに、試合用のトランクス、シューズ、ボクシンググローブを身につけた麗子が、シャドーボクシングを切り上げ、二人に近づいてきた。
「二人とも、準備はいい? OKなら、そろそろ始めましょう。」
二人が元気よく、「はい。」と返事をすると、麗子はにっこりと微笑み、あらかじめ三分、一分にセットされたタイマーのスイッチを入れてから、リングの中に身体を滑り込ませた。
理保とのジャンケンに勝って奇数ラウンド担当になった夏美も、麗子の後から黒いロープをくぐり、青コーナーの方へ歩いていった。第一ラウンドがお休みの理保は、リングの外を回って青コーナーに向かった。
やがて、試合開始の合図であるタイマーのベル音が鳴った。
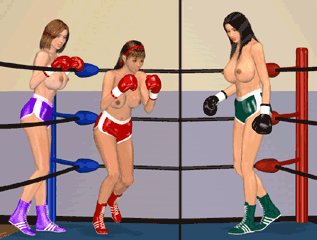
![]() 赤コーナーの麗子の方に一歩目を踏み出そうとした夏美の背中から、理保が、「なっちゃん、頑張って!」と声をかけた。すると、夏美は、一瞬だけ理保の方に振り向き、「まかしといて。」とでも言いたげに小さく頷いてから、青コーナーを飛び出した。
赤コーナーの麗子の方に一歩目を踏み出そうとした夏美の背中から、理保が、「なっちゃん、頑張って!」と声をかけた。すると、夏美は、一瞬だけ理保の方に振り向き、「まかしといて。」とでも言いたげに小さく頷いてから、青コーナーを飛び出した。
麗子も、二人のやりとりを見て微笑んだあと、ゆっくりと赤コーナーを離れた。
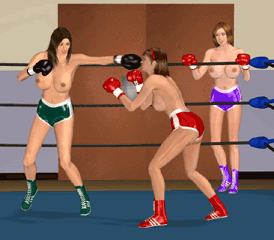
![]() 夏美が麗子との距離を詰めていくと、麗子はいきなり、鞭のような左ジャブを放ち、麗子のパンチが届くまでにはあと数センチあると感じていた夏美の顔を綺麗に弾き上げた。
夏美が麗子との距離を詰めていくと、麗子はいきなり、鞭のような左ジャブを放ち、麗子のパンチが届くまでにはあと数センチあると感じていた夏美の顔を綺麗に弾き上げた。
驚いた夏美は、一歩後ろに下がり、頭の中で、麗子のジャブの射程距離を長めに調整し直した。
「う〜ん、これはちょっと厄介だなぁ。……」
それでも、インファイトに持ち込まないと話にならない。…… 夏美は、何とか麗子の懐に潜り込もうと、どんどん前に出て行ったが、麗子の、射程の長いジャブ、そして、自分のパンチだけが届く距離を保ち続ける、魔法のようなフットワークの前に、夏美は、まったくと言っていいほど、麗子にパンチを当てることができなかった。
やがて、第一ラウンド終了のベルが鳴った。青コーナーに戻ってきた夏美は、悔しそうに、「あー、ダメだぁー。全然中に入れないや。」
と洩らし、理保と交代するために、ロープを跨いだ。
相手が夏美から理保に替わると、麗子は、前のラウンドと戦法をガラリと変え、夏美の攻撃をシャットアウトしたジャブを封印して、相手との距離を取って闘うスタイルの理保を迎え撃った。
適度な距離まで近づいて理保に何発かジャブを打たせ、体重を前足にかけさせて、ジャブを避けながら接近、……
肩でフェイントをかけて理保の腕や脚の動きをコントロールし、素早く理保が強いパンチを打てない角度にステップを踏んでそこからアタック、……
理保は、麗子の技術に翻弄され、次々と麗子に攻め込まれた。
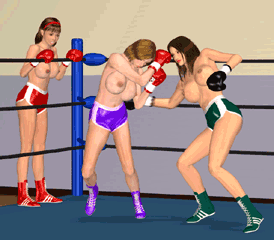
![]() リングの外で二人の闘いを見ている夏美は、麗子が、「こうすれば、もっと効率良く、安全に相手に近づけるのよ。」
ということを、自分に教えてくれているのではないか、ということに気づいた。
リングの外で二人の闘いを見ている夏美は、麗子が、「こうすれば、もっと効率良く、安全に相手に近づけるのよ。」
ということを、自分に教えてくれているのではないか、ということに気づいた。
今後、インファイターとして闘っていくためには、麗子が目の前で披露してくれている技術を、絶対に会得しておく必要がある。……
夏美は、麗子の動きを一瞬たりとも見逃してはならない、と感じた。
ラウンド終了近く、理保は、ニュートラルコーナーに追い込まれてしまった。
コーナーマットを背にした理保は、左腕をスイングしてくるような、麗子の左肩の動きに反応し、両腕をグローブで顔を覆う位置まで上げたが、麗子は左肩の動きを反動にして、理保の脇腹に強烈な右フックを打ち込んだ。そして、理保の左腕が一瞬下がると、そのガードの乱れを見透かしていたかのように、続けざまに放たれた麗子の右フックが、理保のアゴを綺麗に捉えた。
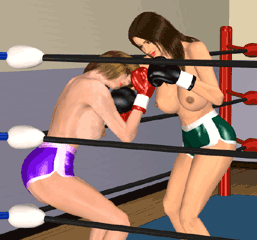 |
 |
理保は、衝撃に耐え切れず、キャンバスにどすんと腰を落とした。
理保が立ち上がったところでタイマーのベル音が鳴り、理保は青コーナーに引き上げてきた。
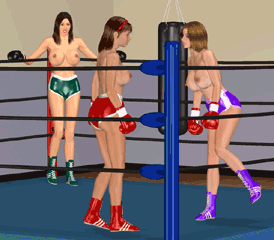
![]() 「あー、やられちゃった。やっぱり麗子先生はすごいな。…… なっちゃん、次のラウンド頑張ってね。」
「あー、やられちゃった。やっぱり麗子先生はすごいな。…… なっちゃん、次のラウンド頑張ってね。」
理保がそう言いながらロープを跨ごうとすると、リングの中に入ってきた夏美が、理保の耳元に顔を寄せてきた。
「ねえねえ、理保ちゃん、…… 私たち、麗子先生にレッスンしてもらってるような気がしない?」
「うん。…… きっとそうだよ。…… 私はなっちゃんみたいなタイプ、なっちゃんは私みたいなタイプの相手が苦手でしょ? 麗子先生は、それをわかってて、苦手なタイプの相手を攻略するためのテクニックをいろいろ見せてくれてるんだと思う。……
麗子先生は、私たちの実力を、真剣勝負の形で確かめておきたいから、今日のスパーを試合形式にする、って言ってたけど、それだけじゃなくて、……
自分の持っているテクニックを、今のうちに、私たちに伝えておこう、って考えてるんじゃないかな。……
私、そんな気がする。」
「…… やっぱり、…… そうなのかなぁ。…… 」
夏美は、理保から麗子へと視線を移した。赤コーナーのコーナーマットに凭れかかって、自分の方に向けられている、少しだけ不敵な麗子の笑顔は、夏美には、「お手本は見せてあげるから、必要だと思う技術は、私から盗んでいってちょうだい。」 と言っているように思えた。
次のラウンド、夏美は、前のラウンドで麗子が見せてくれたテクニックを自分なりに取り入れて、麗子に向かっていった。それでも夏美はなかなか麗子のジャブ網を突破することができずにいたが、ラウンド残り一分ほどのところで、夏美は、自分でも不思議に思えるぐらいに、綺麗に麗子のジャブを避け、自分のパンチが届く距離に麗子を捉えた。
チャンス、とばかりに、夏美は右腕を大きくスイングしたが、夏美の赤いグローブが麗子に当たる前に、麗子の、振り幅の小さい左フックが、強いパンチを打とうと無意識にガードが空いてしまった夏美のアゴに突き刺さった。そして、一瞬、大きく歪んだ夏美の視界が元に戻ったときには、夏美は、キャンバスに横倒しになっていく自分の身体を、両手で庇うしかなくなっていた。
 |
 |
「…… うーん、…… 今のは、…… やっぱり罠だったのかなぁ。…… 」
夏美は、そんなことを考えながら、身体を起こした。
麗子の技術を取り入れたばかりの理保と夏美の動きは、まだまだ付け焼刃の感を否めなかったが、麗子を相手に実践を重ねていくに連れて、少しずつ実を結び始めるようになっていった。

![]() その甲斐もあってか、麗子は、ラウンドごとの五分間で、リフレッシュして向かってくる若い二人を、徐々に押さえ込めなくなってきた。
その甲斐もあってか、麗子は、ラウンドごとの五分間で、リフレッシュして向かってくる若い二人を、徐々に押さえ込めなくなってきた。
理保と夏美が、それぞれ五度目の担当ラウンドを迎える頃には、理保のジャブがびしびしと麗子の顔を弾き、夏美が半ば強引に麗子の懐に潜り込んで、麗子のボディや顔面へと、重いパンチを叩き込むシーンが増えてきた。
夏美の六ラウンド目の担当となる第十一ラウンドのラスト間際、夏美は、完全に足の止まってしまった麗子を赤コーナーに追い込み、ラッシュをかけた。
麗子は、二十発近い夏美の連打に耐え凌いでいたが、夏美の強烈なボディフックを食らい、ついに両膝を折り、キャンバスに両手をついた。
 |
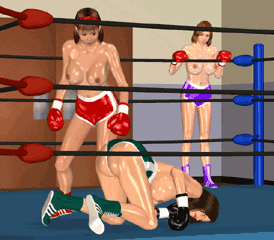 |
麗子は、しばらく四つん這いになったまま、苦痛に顔を歪めていたが、やがて、心配そうに自分を見つめている夏美に向かって笑顔を取り繕い、「まだ大丈夫。試合を続けるわよ。」と言ってから、ゆっくりと立ち上がった。

![]() ラウンド終了を告げるベルが鳴り、夏美が青コーナーに戻っていくと、理保が心配顔で話しかけてきた。
ラウンド終了を告げるベルが鳴り、夏美が青コーナーに戻っていくと、理保が心配顔で話しかけてきた。
「ねぇ、なっちゃん、…… 麗子先生、大丈夫かな。……」
「うーん、…… 口では大丈夫って言ってるけど、かなり効いてるはずだよ。……」
ロープを跨いでリングの中に入ったものの、赤いコーナーマットに凭れかかって、苦しそうに荒い呼吸を繰り返している麗子の姿を見ていると、理保は、これ以上麗子を攻撃する気には、あまりなれなかった。すると、浮かない表情の理保の心情を読み取った夏美が口を開いた。
「辛いと思う気持ちはわかるけど、…… でも、ちゃんと麗子先生にとどめを刺さなきゃダメだよ、理保ちゃん。……
前のラウンド、見てたからわかると思うけど、麗子先生は、もうKO寸前まで来てる。だからこそ、私はそういう相手をきっちり仕留めることができます、ってことを、麗子先生に伝えなきゃ。……
私は、…… 麗子先生はそれを望んでいると思う。」
そう言い切った夏美に、理保は、「でも、……」 と言い返しかけたが、少しの間、黙って俯いたあと、理保は、ふっ切れたような笑顔を夏美に向けた。
「そうだね。…… 先生が、このスパーを試合形式にしよう、って言ったのも、きっとそういうことなんだ。……
私、やるよ。最高のパンチを叩き込んで、きっちり麗子先生をKOして見せる。」
ラウンド開始のベル音が鳴り、青コーナーを飛び出した理保は、激しく麗子を攻め立てた。そして、ラウンド開始から一分ほどが経ったとき、やや遠目から放った理保の左ストレートが麗子の顔面にヒットすると、麗子の動きが一瞬止まり、少しだけ腰の位置が落ちた。ここでフィニッシュだ、というきっかけを感じ取った理保は、素早く踏み込み、一気に畳み掛けた。
 |
 |
「ラブ・アッパー!!」
得意のコンビネーションブローの最後を締める左アッパーが、綺麗に麗子のアゴを抉ると、麗子の両膝が砕けるように折れた。

![]() 麗子が、青コーナーに頭を向けるようにして、大の字に倒れると、理保は、すぐに麗子の側に両手のグローブをつき、「麗子先生、大丈夫ですか?」
と声をかけた。
麗子が、青コーナーに頭を向けるようにして、大の字に倒れると、理保は、すぐに麗子の側に両手のグローブをつき、「麗子先生、大丈夫ですか?」
と声をかけた。
麗子は、やがて少しだけ頭を持ち上げ、上体を起こす素振りを見せたが、すぐに頭をキャンバスに落とし、心配そうに自分を見つめる二人の顔を交互に見たあと、大きく息を吐き出した。
「……参った。降参よ。…… 二人とも、本当に強くなったわね。」
理保は、麗子の意識がはっきりしていること、これ以上麗子を殴らなくてもいいということの安心感に、ほっと溜息を洩らした。
麗子は、全身の力を抜き、目を閉じた。この子たちは、もう私がいなくても、一人前のボクサーとしてやっていける。……
麗子は、自分に課せられた最後の使命をやり遂げた達成感を噛み締めながら、キャンバスに横たわることの心地良さに浸った。
夏美もロープを跨いでリングの中に入ってきた。そして、麗子の傍らにひざまずくと、顔を向けた理保に目配せした。
両方の乳首に生暖かいものが触れたので、麗子が驚いて目を開けると、理保と夏美が、さかんに麗子の乳首をしゃぶっているところだった。
「ちょっ、…… ちょっと、あなたたち、何してるの?」
麗子がそう問いただすと、夏美がわずかに顔を上げた。
「理保ちゃんと話してたんですよ。試合が終わったら、今までのご恩返しに、麗子先生を心ゆくまで愛してあげるって。……
さあ、麗子先生、身体の力を抜いて、…… 私たちの愛を受け取ってください。……」
麗子は、「いや、…… 私は、……」 と言いかけたが、夏美が再び麗子の乳首を口に含み、それを舌先でクリクリと転がすと、麗子は小さな喘ぎ声を洩らした。そして、ほどなく、夏美は麗子の股間に腕を伸ばし、汗でぴったりと麗子の身体に貼り付いているトランクスの上から、麗子の股間を優しくさすり始めると、麗子の口から洩れる声が、徐々に大きくなってきた。
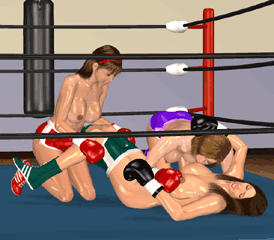
![]() 麗子の昂ぶりを察知した夏美は、麗子の足元へと移動し、麗子のトランクスにグローブをかけて、それを引きずり下ろし始めた。
麗子の昂ぶりを察知した夏美は、麗子の足元へと移動し、麗子のトランクスにグローブをかけて、それを引きずり下ろし始めた。
麗子は、慌てて、自分のグローブでトランクスを抑えようとしたが、夏美は、微笑みながら、「大丈夫。裸になったら、もっと気持ちいいですよ、麗子先生。」
と、諭すように麗子に話しかけ、麗子の濃いグリーンのトランクスを、一気に脱がし去った。
すでに、ぴんぴんに乳首を勃起させている麗子は、さかんに身体を捩りながら、必死に昂ぶりを抑えていた。しかし、夏美が、左手のグローブの親指を、ぷっくりと膨らんだ麗子の宝珠にぴったりと当て、激しく擦ると、麗子は、ついに我慢の限界を突破してしまった。

![]() 「いやぁぁ、…… ああああぁぁぁーーーー!!」
「いやぁぁ、…… ああああぁぁぁーーーー!!」
麗子の切ない叫び声とともに、全身を固く硬直させた麗子の股間から、大量の熱い汁が一気に噴き出し、夏美の赤いグローブを濡らした。
浮いていた麗子の腰が、どすんとキャンバスに落ちると、だらしなく四肢を投げ出した麗子の身体が、ぴくんぴくんと震えた。
やがて、軽い痙攣も収まり、乱れていた呼吸が整ってくると、麗子は、少し怯えたような眼差しで、若い二人を見つめた。
「…… 何?…… 今のは、…… 私はどうなってしまったの?……」
独り言のように、そう口にした麗子に、夏美は満足気な笑みを向けた。
「今のはですね、…… アクメとか、オルガズムスとか言われているもの。……
ま、簡単に言うと、先生は、イっちゃったんです。」
「…… イった?…… 私が?…… 今のが、そうなの?……」
「やっぱり初めてだったんですね、麗子先生。そんな気がしてました。…… で、どうでしたか? すっごく気持ち良かったでしょう?」
麗子は一瞬答えに詰まったが、やがて、恥ずかしそうにコクリと頷いたあと、思い出したように理保の方に視線を向けた。
「あなたたち、いつも、練習が終わって私がいなくなったあと、二人で何かゴソゴソしてたみたいだったけど、こんなことをしてたのね。」
「…… それは、…… えっと、…… なっちゃんが、とても上手だから、……」
理保が、少し恥ずかしそうに答えると、夏美がそれを遮った。
「まあ、いいじゃないですか。誰かが嫌な思いをするわけでもないし。…… それよりも、もう一度、今度は三人で一緒に愛し合うってのはどうですか? 麗子先生。」
そう言われて、麗子は少し考えてみた。
私は、今日でボクシングとお別れ。数学の先生に戻ったら、理保や夏美と会う機会もあまりなくなるだろう。……
それなら、今までボクシングに携わってきた最後の想い出として、二人と愛を分け合うのもいいかも知れない。……
麗子の答えは、笑顔となって現れた。それを感じ取った夏美は、「じゃぁ決まりですね。」
と笑顔で応じ、自分の赤いトランクスを脱ぎ始めた。
「それじゃぁ、麗子先生をKOした理保ちゃんに、勝利者賞ということで、気持ち良くなってもらうっていうのはどうですか、麗子先生?」
「あ、それはいいかも知れないわね。じゃ、そうしましょうか。」
理保が夏美に合わせてトランクスを脱いでいる間、夏美と麗子は、理保の横で、そんなことを話し合っていた。
「そういうことに決まったから、今度は理保ちゃんの番だよ。さ、横になって。」

![]() 夏美は、少し驚いている理保にキスしたあと、理保の身体を舐めながら、理保を優しく押し倒し、理保の太腿を抱えるようにして、理保の股間に顔を埋め、理保の女性自身を舌先でまさぐった。
夏美は、少し驚いている理保にキスしたあと、理保の身体を舐めながら、理保を優しく押し倒し、理保の太腿を抱えるようにして、理保の股間に顔を埋め、理保の女性自身を舌先でまさぐった。
夏美に続いて、麗子も理保の身体に覆い被さるようにして、理保の乳房を愛撫し始めた。やや勃ち始めた乳首に麗子の舌触りを感じると、理保は、小さな喘ぎ声を上げ、熱い吐息を洩らした。