

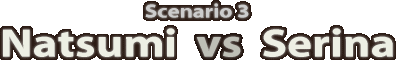
理保と夏美は、試合後すぐに、『理保ちゃん』、『なっちゃん』と呼び合うほどの、親しい間柄になった。そして、試合のひと月後には、理保の師である麗子の指導の下、お互いをパートナーとして数度のスパーリングを行うまでになっていた。大の親友、そして最良のスパーリングパートナーを得たことで、理保も、夏美も、とても満ち足りた日々を送っていた。
理保と夏美の試合から一ヶ月半ほどが経ったある日の夕方。その日の勤務を終えた夏美は、都内のとあるレストランのドアを開け、すでに到着していた理保と同じテーブルについた。
この日の十日ほど前、夏美は、自分と同じようにデビュー戦を勝利した選手と試合を行い、鮮やかな一ラウンドKO勝利を収めていた。この日は、夏美のための、『二人だけの祝勝会』として、理保が夏美を招待したものだった。
「なっちゃん、KO勝ちおめでとう。約束どおり、今日は私のオゴリだから、何でも好きなものをお腹一杯食べてね。」
「…… ううん。…… それがね、……」
夏美のことだから、間違いなく、「ホントに好きなものを好きなだけ食べていいのね? えへへへ。」という感じの返事が返ってくると考えていた理保は、夏美の歯切れの悪い反応に首をかしげた。
「ん? どうしたの? なっちゃん。お腹の調子でも悪いの?」
「…… そうじゃなくて。…… 実は、あさって、BBIの『二週前検量』で。……」
「ええーっ? 二週間後って言うと、Kホールの定期興行だよね? …… なっちゃん、また試合なの?」
「…… うん。急に決まったの。…… フライ級で、一人、相手の居ない選手が出ちゃったんで、私に話が来たみたい。……
ってことで、今日は思う存分食べる、ってわけにはいかないんだ。理保ちゃんのオゴリだって言うから、今日は、うーんと高いものを、お腹が破裂するぐらい食べてやろうと思ってたんだけどね。」
「そうなんだぁ。…… でもさぁ、なっちゃん。試合のペース、早過ぎない?」
「うーん、…… でもほら、前の試合は一ラウンドで終わっちゃったし、……」
「ああ、それもそうねぇ。」
「でね、院長に話を持ってったら、今はナースのスケジュールに余裕あるから大丈夫だ、って言ってくれたのね。……
クリニックの方の事情もあるから、私、試合できるときに、できるだけこなしておきたいんだ。」
「なるほどね。…… で、相手はどんな人なの?」
「それがね、何でも、お水関係の店で働いてる人みたいなんだよね。」
「それって、ホステスさんとか、ってこと?」
「うん。そうみたい。…… BBIの審査を通ったばかりで、今度の、私との試合がデビュー戦なんだって。」
「ふーん、変わった人ねぇ。…… でも、考えてみれば、私はついこないだまでアイドル業専業だったわけだし、なっちゃんは現役バリバリの看護婦さん。……
あんまり人のことは言えないわね。うふふふふ。」
二人がそんな会話をしていると、店の給仕が注文を取りに来た。夏美は、量こそ抑えたものの、店で一番高いステーキのセットを頼んだので、理保もそれに合わせて、同じものをオーダーした。
食事のあいだ中、夏美は、理保が用意してくれたオゴリの席で、腹いっぱい食べられないことを悔しそうにしていた。理保が、「次の試合にちゃんと勝ったら、今度はホントに好きなだけ食べさせてあげるから」となだめると、夏美は、「ホントに?
絶対よ。約束よ。」と念を押してきた。理保には、そんな夏美らしい仕草が、少し可笑しかった。
そして、『不完全燃焼のタダ飯』から二週間後、夏美は、いつもの赤いトランクス、赤いシューズを身につけ、デビュー三戦目のリングに上がった。
夏美は、自分への声援に声援にいちいち反応し、笑顔を向けて手を振りながら、リングに向かって歩いてくる瀬里奈の行動を、特に不自然だとは感じなかった。お水関係の仕事をしてるわけだし、名前を呼ばれたら笑顔で応対、そんなものなのかなぁ、と、夏美は思った。

![]() しかし、それがリング上まで続くならまだしも、レフェリーに試合前の注意を受けているときでも変わらなかったことに、夏美はとても驚いた。瀬里奈がこの日デビュー戦であることを意識してか、レフェリーが丁寧にルールの説明をしていても、観客席から声がかかると、瀬里奈は躊躇することなくその声の方を向き、笑顔を振り撒いて手を振った。
しかし、それがリング上まで続くならまだしも、レフェリーに試合前の注意を受けているときでも変わらなかったことに、夏美はとても驚いた。瀬里奈がこの日デビュー戦であることを意識してか、レフェリーが丁寧にルールの説明をしていても、観客席から声がかかると、瀬里奈は躊躇することなくその声の方を向き、笑顔を振り撒いて手を振った。
「この人、…… もしかして、天然なのかしら?……」
夏美は、呆気に取られた表情で、自分とレフェリーを気にも留めずに観客席からの声援に応える瀬里奈を見つめた。
試合前の話の最後に、レフェリーがグローブを合わせてお互いに挨拶をするよう指示すると、瀬里奈はそのとき自分にかけられた声援の声の主の方を向いたまま、両拳を覆っている黒いグローブを、夏美のグローブに軽く当てただけで、そのままくるりと後ろを向いてしまった。
これからボクシングの試合という形で殴り合う相手の自分よりも、周囲の声援の方が重要。……
そう感じた夏美は、瀬里奈に対して、少しマイナスの感情を持った。

![]() 「うーん、なんか調子狂っちゃうなぁ。…… あの人、試合だっていうのに、あんなにべっとり口紅つけてるし、……
うん、ちょっとボクシングの厳しさを教えてあげる必要があるわね。……」
「うーん、なんか調子狂っちゃうなぁ。…… あの人、試合だっていうのに、あんなにべっとり口紅つけてるし、……
うん、ちょっとボクシングの厳しさを教えてあげる必要があるわね。……」
BBIのスタッフにマウスピースを咥えさせてもらった夏美は、相変わらず周囲の歓声に応えるだけで、なかなか自分のコーナーに戻って試合の準備に入ろうとしない瀬里奈を、険しい目で睨んだ。
瀬里奈は、ボクシングの試合中だとは思えない、試合前と同じ感じの少しだらしない笑顔を満面に浮かべたまま、夏美に向かってまっすぐ近づいてきた。

![]() その瀬里奈をパンチの射程に捉えた夏美は、『ボクシングの厳しさを教えてやる』
という思いを込め、ややストレート気味のジャブを放とうとした。
その瀬里奈をパンチの射程に捉えた夏美は、『ボクシングの厳しさを教えてやる』
という思いを込め、ややストレート気味のジャブを放とうとした。
「えっ?」
夏美が腕を伸ばす直前に、瀬里奈は上半身をすっと沈み込ませた。夏美の左拳の赤いグローブはターゲットを外れ、瀬里奈の右肩の上あたりを通過した。
瀬里奈の動きは、パンチを避けるための、上半身を折り曲げるようなものでなかった。夏美には、その瀬里奈の動きが何を意図するものなのか、瞬時には判断できなかった。

![]() 次の瞬間、瀬里奈は、曲げていた両膝を一気に伸ばし、大きく振りかぶっていた左腕を鉤型に曲げたまま、思い切り振り上げた。
次の瞬間、瀬里奈は、曲げていた両膝を一気に伸ばし、大きく振りかぶっていた左腕を鉤型に曲げたまま、思い切り振り上げた。
「おしぼり入りまぁ〜す!」
瀬里奈の、全身の反動を使って放たれた左アッパーが、夏美のアゴをまともに捕らえた。その衝撃に、夏美の身体が大きく反り返った。
「まったく、この人は、いきなり、なんていう大袈裟なパンチを……」
夏美は、あまりにも常識はずれな瀬里奈の攻撃を苦々しく思った。同時に、その攻撃に対応できなかったことを反省した。
この人は何をするかわからない。しばらく様子を見なきゃ。…… 瀬里奈との距離を置こうと夏美が後ろ下がろうとしたとき、夏美は自分の身体が大きく傾いていくのを感じた。

![]() 「えっ?…… あ、…… あれっ?……」
「えっ?…… あ、…… あれっ?……」
夏美は慌てて足を繰り、その場に踏ん張ろうとしたが、瀬里奈の『大袈裟なパンチ』は、夏美の両脚の自由を奪い取ってしまっていた。
キャンバスに腰を落とした夏美と、相変わらずだらしのない笑顔のまま、夏美に襲い掛かろうとした瀬里奈との間に、レフェリーが割って入った。

![]() 「ダウン。…… ワン、…… トゥー、…… スリー、……」
「ダウン。…… ワン、…… トゥー、…… スリー、……」
夏美はすぐに立ち上がり、レフェリーにファイティングポーズを向けたものの、夏美の両脚は、まだ少し震えたままだった。
夏美は、脚だけでなく、全身の運動機能が破壊されつつあることをぼんやりと自覚していたが、それは夏美にとって、あまりにも受け入れ難い現実だった。
レフェリーがダウンカウントをエイトで止め、試合続行を指示すると、瀬里奈は控えていたニュートラルコーナーを飛び出し、金のコーナーを背負った夏美に、すぐに攻撃を仕掛けてきた。
夏美の闘争心は、夏美に『応戦』という選択肢を取らせた。しかし、夏美の身体は、相手の攻撃に対抗できるだけの機能を、まだ取り戻してはいなかった。

![]() 「指名入りまぁ〜す!」
「指名入りまぁ〜す!」
瀬里奈の強烈な右フックが夏美の顔面を襲った。その衝撃に、両腕を中途半端な位置に上げた状態で、夏美の動きが完全に止まった。
「指名入りまぁ〜す!」
「指名入りまぁ〜す!」
夏美は、叩き下ろすような瀬里奈の右フックを、まともに貰い続けた。

![]() 瀬里奈の四発目の右フックを食らうと、夏美の身体が大きく右に傾いた。そして、夏美は、そのまま、ごろりとキャンバスに転がった。
瀬里奈の四発目の右フックを食らうと、夏美の身体が大きく右に傾いた。そして、夏美は、そのまま、ごろりとキャンバスに転がった。
「ダウン! ニュートラルコーナーへ!」
レフェリーは、ダウンした夏美に身体を向け、一歩踏み込んだ瀬里奈を制すると、夏美の側で片膝をついて、この日二度目のダウンカウントをスタートさせた。

![]() 夏美はすぐに上体を起こし、近くのロープにグローブをかけて、立ち上がろうともがき始めたが、ダメージの深刻さを物語るように、夏美の全身は、まだ小刻みに震えていた。
夏美はすぐに上体を起こし、近くのロープにグローブをかけて、立ち上がろうともがき始めたが、ダメージの深刻さを物語るように、夏美の全身は、まだ小刻みに震えていた。
「…… フォー、…… ファイブ、…… シックス、……」
ニュートラルコーナー近くでは、瀬里奈が再び観客席に向かってポーズを取り、笑顔を振り撒いていた。
夏美は何とかカウントエイトまでに立ち上がったものの、両手のグローブでロープを掴んで、やっと身体を支えている状態で、瀬里奈の連打に吹き飛ばされた表情も、まだ戻っていなかった。

![]() レフェリーの、「まだできるか?」 の問いかけに、夏美が首を縦に振り、レフェリーが、夏美に、ファイティングポーズを取るように要求すると、一瞬の不自然な間のあと、夏美は、こわごわといった感じの動きで、掴んでいるロープから手を離し、両腕を胸の前に構えた。
レフェリーの、「まだできるか?」 の問いかけに、夏美が首を縦に振り、レフェリーが、夏美に、ファイティングポーズを取るように要求すると、一瞬の不自然な間のあと、夏美は、こわごわといった感じの動きで、掴んでいるロープから手を離し、両腕を胸の前に構えた。
試合が再開される気配を感じ取った瀬里奈は、夏美の方に身体を向け、その場で軽快なステップを踏み始めた。
レフェリーが試合再開を宣言すると、瀬里奈はきらきらと瞳を輝かせながら、金のコーナーの前に立ち尽くす夏美に襲い掛かってきた。
夏美は、瀬里奈の右フックに合わせて、身体を丸め、胸の高さに上げていたグローブで顔をガードしようとしたが、夏美の運動機能は、すでに、瀬里奈の動きにまったくついていけなくなるほどまでに破壊されていた。
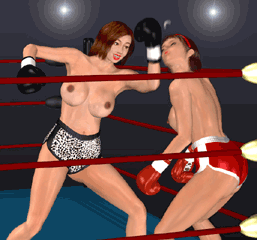
![]()
瀬里奈の右フック、そして間髪を入れずに放たれた左アッパーが夏美の顔面を捻じ曲げると、夏美の腕は、力なくストンと落ちてしまった。
「お帰りでぇ〜す!!」
瀬里奈は、上体を大きく捻り、身体全体を使って、もう一度、得意の左アッパーを突き上げた。
瀬里奈の黒いグローブが、がらあきになった夏美のアゴにめり込んだ。そして、次の瞬間には、夏美の口から、白いマウスピースが高々と舞い上がっていた。
瀬里奈のフィニッシュブローを食らい、夏美の身体は、金色のコーナーマットをずるずると滑り落ちていった。そして、夏美は、下段ロープのコーナーマットに背中を凭れかけて、両腕を身体の前にだらりと垂らし、だらしなく大股を開いた格好で動かなくなった。

![]() レフェリーが夏美の顔を覗きこむと、夏美は完全に白目を剥き、マウスピースの外れた口から涎を垂らしていた。レフェリーは即座に試合終了をコールすると同時に、ドクターにリングに上がり、夏美の身体をチェックするよう要請した。
レフェリーが夏美の顔を覗きこむと、夏美は完全に白目を剥き、マウスピースの外れた口から涎を垂らしていた。レフェリーは即座に試合終了をコールすると同時に、ドクターにリングに上がり、夏美の身体をチェックするよう要請した。
試合終了のゴングが打ち鳴らされると、瀬里奈は、嬉嬉とした表情を顔一杯に浮かべて何度も拳を振り上げ、全身でKO勝利の喜びを表現した。
理保は、飛び出すようにしてタクシーを降り、ちらりと腕時計を覗き込んでから、そこからKホールへの短い道のりを懸命に走った。
夏美の試合を観戦するために、理保は、この日の午後はスケジュールを空けておいた。しかし、午前中に終わるはずだったグラビア撮影の仕事が二時間近く伸び、さらにタクシーに乗ったあと、思いもよらない交通渋滞にぶつかってしまったこともあって、理保がKホールに着いたのは、ちょうど夏美の試合が予定されている時間と、ほぼ同じだった。
「もう始まっちゃってるかも知れないな。……」
また腕時計に目を遣って時間を確認した理保は、そんなことを思いながらKホールの入場ゲートを通り抜け、観客席へ抜ける短い通路を小走りに進んだ。その最中、理保は、会場から聞こえてくる騒音に、やや異様な雰囲気を感じ取った。理保には、その音が、試合中という感じにも、試合と試合の間のインターバルという感じにも思えなかった。
嫌な胸騒ぎを覚えたまま、会場全体が見渡せる場所まで辿り着いた理保がリングの上に見たものは、誇らしげに腕を掲げながらリングの中を練り歩いている、豹柄のトランクス、黒のグローブとシューズを身につけた女ボクサーだった。

![]() 「えっ?」
「えっ?」
理保には、その状況が何を意味しているのか、とっさには理解できなかった。
理保がさらにリングの方へ進み出て、辺りを見回すと、BBIのスタッフが、赤いコスチュームの選手を担架で運んでいる光景が目に入った。
「なっちゃん!!」
理保は、そう叫ぶと、担架に乗せられてリングから運び出される途中の夏美に駆け寄った。
「なっちゃん!! …… どうしたの?! …… 何があったの?!!」
夏美は、理保がそばに居ることに気づくと、薄く開いた瞳をゆっくり理保の方へ向け、わずかに唇を動かした。しかし、夏美の口から洩れたのは、言葉にならない弱々しい声と、吐息だけだった。
理保がさらに夏美に詰め寄ろうとすると、理保が今会場に到着したばかりだということに気づいていたBBIのスタッフが、理保を制した。
「橘選手は試合開始早々にKOされ、しばらくの間、完全に失神していました。……
今は少し意識が戻りましたが、まだ危険な状態を脱していません。すぐに病院に運び、精密検査と万全の手当てを受ける必要があります。」
「…… そんな、……」
理保が、抱きつくようにして自分を制したスタッフの顔を、縋るような瞳で見つめると、彼女は、とても申し訳なさそうに、理保に向かって小さく頷いた。
そうしている間にも、夏美を乗せた担架は、どんどん理保から遠ざかっていっていた。
「…… なっちゃん。…… しっかりして、……」
理保には、会場の外へと続く通路に消えてゆく夏美を見つめ、搾り出すようにそれだけ言うことしかできなかった。