


プロボクサー宣言をした理保は、忙しいスケジュールの中、できる限りの時間をトレーニングに割き、精力的に活動を続けていた。ある日、撮影の仕事を終えたあと、二時間ほどを激しいトレーニングに費やした理保は、腰に軽い痛みを覚え、都内某所の、とある整形外科クリニックを訪れていた。
このクリニックの院長は、ボクシングに関して非常に造詣が深く、BBIが都内で行う興行でしばしばリングドクターを務め、また有能なスポーツ整形外科医でもあった。BBIの選手をはじめ、多くのスポーツ選手がこのクリニックを利用しているということで、理保が本格的にボクサーの活動を始めるに当たり、麗子が理保に紹介したものだった。それ以来、理保は、このクリニックを週に二、三度の頻度で利用していた。
デビュー戦を予定している、BBIの都内興行まであと三週間を切ったことだし、そろそろ対戦スケジュールが発表になるのではないか。……
その日、理保は、そんなことを考えながら、腰部の牽引とマッサージで、一時間ほどの時間を院内で過ごした。
クリニックでの予定を終えた理保は、出口に向かって歩きながら、病院内ということで電源を切っていた携帯電話をバッグの中から取り出そうとした。
「理保さぁん!」
後ろから自分の名前を呼ぶ声の方に理保が振り向くと、ナース服を身に纏った一人の若い看護婦が、理保の方へ小走りに駆け寄って来ていた。『橘』と書かれた名札を胸につけたその看護婦は、理保の前で立ち止まり、こぼれんばかりの笑顔を理保に向けた。
理保は、この若い看護婦のことを、とても気に入っていた。これまでに直接話をする機会はあまりなかったが、クリニックを利用する人に、明るい声で積極的に話しかける光景を何度も目にしていたし、ケラケラと大きな声でよく笑う。忙しそうに院内を駆けずり回っていても、疲れたという表情を見たことがない。まるで、『元気』という文字がナース服を着ているようだ、と、理保は常々思っていた。
「よろしくお願いしますねっ。」
その看護婦が、唐突に大きな声でそう話しかけてきたので、理保は、「あ、はい、……
こちらこそ、……」と生返事をしたが、理保には、何が「よろしく」なのか、よくわからなかった。理保の合点のいかない表情を見た看護婦は、少しだけしたり顔になった。
「さっき、Kホール大会の試合スケジュールのファックスが、クリニックに届きました。対戦予定も書いてありましたよ。」
「えっ? ほんとに?…… じゃ、私にももう連絡来てるかな。」
理保は、バッグの中から携帯電話を掴み出し、電源を入れた。そう言えば、このクリニックの院長さんは、よくKホールで行われる興行のリングドクターに呼ばれるみたいだし、今度の大会で、この看護婦さんもお手伝いにくるのかな、と理保は思った。
理保の携帯には、未読のメールが何通か届いていたが、BBI関係のものは、その中に混じっていなかった。理保は携帯電話を折りたたみ、バッグの中に戻した。
「あーん、私んとこにはまだ連絡ないや。…… ねぇ、橘さん、橘さんはもう、私の相手が誰だか知ってるんですよね。……良かったら、教えていただけません?」
「ええ。…… 理保さんの知ってる人ですよ。」
「へぇー。どんな人なのかなー。……」
「ここにいますよ。」
「え?」
理保は驚いて、辺りを見回してみた。クリニックのロビーには、理保と同じ世代の女性が数人居たが、その中に、看護婦の言う、『知ってる人』
は、一人も居なかった。理保が思案顔でその看護婦に視線を戻すと、彼女は、少しいやらしいぐらいににっこり微笑んだ。
「ほらぁ、目の前に立ってるじゃないですかぁ。…… 私ですよ。わ、た、し。」
「えっ?…… ええぇっ?!」
明るい看護婦は、人差し指で自分の顔を指していた右手を、ナース服のポケットへと移して、そこから取り出した一枚の紙を、目を真ん丸に見開いて自分の顔を見つめている理保に手渡した。理保が四つ折りになっているその紙を開くと、そこにはKホール大会の試合スケジュールが記載されていた。そして、自分の名前の横に書いてある対戦相手の名前の欄には、はっきりと、『橘夏美』と記されていた。
「私もね、去年BBIの審査通ったんですよ。でも、もうすぐデビュー戦、ってところで、クリニックのベテランナースが、家の事情で急にやめることになっちゃって、ボクシングどころじゃなくなっちゃったんです。……
で、新しいナースが最近やっと仕事に慣れてきたんで、院長に許可をもらって、Kホール大会にエントリーしてたんですよ。……」
理保は、ようやく事情を呑み込んだ。確かに、この人なら、ボクシングぐらいはやりかねない、と理保は思った。
「…… でも、デビュー戦の相手が理保さんなんて、…… 嬉しいな。えへへへ。」
夏美はもう一度嬉しそうに笑い、理保の両手を掴んだ。
「じゃ、改めて。…… 理保さん、よろしくお願いしますね。」
「はい、こちらこそ。橘さん、いい試合をしましょう。」
理保も夏美の手を強く握り返し、にっこりと微笑んだ。
デビュー戦の対戦相手がはっきりとイメージできたことで、理保は翌日から、より身を入れてトレーニングに励むことができた。
相手が夏美なら、変な気負いを感じることなく、全力でぶつかることができる。……
理保は、夏美がデビュー戦の相手であることを嬉しく思った。
試合までの日々はあっという間に流れ、いよいよ理保がリングデビューを果たす日がやって来た。
五月なかばの、よく晴れた日曜日。二部構成で行われたBBI興行Kホール大会の第一部は、予定通り、午後一時に第一試合開始のゴングが鳴った。八試合が組まれた第一部は、すべてデビュー戦を迎える選手同士の対戦が組まれており、理保と夏美の試合は、その中の最後の第八試合、言わば、第一部のメインイベントという形で扱われていた。

![]() 「ゴールドコーナー〜〜、…… 108パウンド二分の一ぃ〜〜、…… 双葉ぁ〜〜、理ぃ〜〜保ぉ〜〜〜〜!!」
「ゴールドコーナー〜〜、…… 108パウンド二分の一ぃ〜〜、…… 双葉ぁ〜〜、理ぃ〜〜保ぉ〜〜〜〜!!」
初めて受けたリングコールに合わせ、背にしていた金のコーナーを離れてリングのほぼ中央に進み出た理保は、両手を上げ、さかんに送られてくる声援に応えた。
先にリングコールを終えた夏美は、銀のコーナー近くで小さく身体を動かしながら、その様子に見入っていた。

![]() 試合前の注意を受けるため、理保と夏美は、リングの中央で対峙し、デビュー戦の相手に、引き締まった表情を向け合っていた。
試合前の注意を受けるため、理保と夏美は、リングの中央で対峙し、デビュー戦の相手に、引き締まった表情を向け合っていた。
「…… デビュー戦らしい、クリーンなファイトを期待しています。それではグローブを合わせて。」
やがて、レフェリーの話が終わると、二人は少しだけ表情を崩し、小さく頷き合った。
理保が両手を差し出すと、夏美は理保の赤いグローブを力強くタップした。理保には、「最高のデビュー戦にしよう」という、夏美の意思が込められているように思えた。そして、理保も、同じ思いを込めて、夏美のグローブにタップを返した。
コーナーに戻った二人が白いマウスピースを咥えると、間もなく、「ラウンド・ワン」のコールがかかり、大きな声援の中、試合開始のゴングが鳴った。

![]() 理保と夏美のボクシングセンスの高さは、この日、それまでに行われていた七試合に比べ、一段も二段も上のファイトを展開していた。
理保と夏美のボクシングセンスの高さは、この日、それまでに行われていた七試合に比べ、一段も二段も上のファイトを展開していた。
長いリーチを活かすために、ジャブを多用しながら距離を取って闘いたい理保に対し、夏美はぐいぐいと前に出て、次々と鋭いフック、ストレートを放ってきたが、理保は大きなダメージを受けることなく、夏美の積極的な攻撃をうまくやりすごしていた。
しかし、第一ラウンド終了のゴングが鳴り、金のコーナーに戻った理保は、手数、パンチの正確性ともに、自分がやや劣勢だったことを自覚していた。
「第一ラウンドは、夏美さんにポイント取られちゃったかな。……」
理保は、そんな感触を抱きながら、公式の試合で初めて経験する、一分間のインターバルを過ごした。
続く第二ラウンドも、理保は夏美の攻撃をなかなか跳ね返すことが出来ず、やや不利な展開を強いられていた。この状況を打破するため、ラウンドの中盤ぐらいから、理保は、ヒットアンドアウエイに徹するのではなく、ときおり夏美との打ち合いに応じるようになった。
第二ラウンドの残りが四十秒ほどになったとき、理保の右ストレートがカウンターとなって夏美の顔面を捉えた。

![]() 強烈な衝撃に、一瞬動きの止まった夏美の前で、理保はなめらかに上半身を捻り、鉤型に曲げた左腕を突き上げた。
強烈な衝撃に、一瞬動きの止まった夏美の前で、理保はなめらかに上半身を捻り、鉤型に曲げた左腕を突き上げた。
「プリティー・アッパー!」
夏美の顔が真上に弾け上がった。そして、理保の左拳には、ターゲットを的確に打ち抜いたあとの、会心の手応えが残った。

![]() 夏美の両膝の力が抜け、夏美は、キャンバスにどすんと尻餅をついた。
夏美の両膝の力が抜け、夏美は、キャンバスにどすんと尻餅をついた。
「や、…… やったぁ。……」
理保は、腕をファイティングポーズの位置に上げたまま、夏美を見下ろしていた。あまりにも綺麗な形で奪い取ったダウンに、理保の頭の中は、一瞬真っ白になっていた。
「ダウン! ニュートラルコーナーへ!」
レフェリーの声に、ようやく我に返った理保は、悔しそうに自分を見上げている夏美のそばを離れ、レフェリーの指示通りに、ニュートラルコーナーへ向かった。

![]() 「…… ファイブ、…… シックス、…… セブン、……」
「…… ファイブ、…… シックス、…… セブン、……」
ニュートラルコーナーで待機している理保は、身体を軽くゆすりながら、ダウンをした夏美の様子を窺っていたが、夏美は特に慌てるでもなく、自分に向けられたダウンカウントが後半に入るまで、キャンバスに腰を下ろしたまま呼吸を整えた。そして、カウントエイトに合わせて立ち上がり、レフェリーにしっかりしたファイティングポーズを向けた。
試合が再開されると、理保はチャンスを更に広げようと、夏美に襲い掛かったが、夏美はダウンのダメージをまったく感じさせずに応戦し、第二ラウンドの残りは、ほぼ互角の攻防で終わった。
第三ラウンド、ダウンのダメージを完全に払拭した夏美は、更にアクセルを吹かし、先のラウンドよりも激しく理保を攻め立てた。

![]()
理保も必死に応戦するものの、接近戦で夏美がときおり放ってくる強烈なボディブローに体力を削り取られた理保は、第四ラウンド、第五ラウンドと試合が進んで行くに連れ、夏美のプレッシャーを徐々にかわし切れなくなってきた。
理保は、何度もロープ際やコーナーに追い詰められ、夏美の連打を浴びた。
防戦一方の第五ラウンドは、理保にはとても長く感じられた。最終ラウンドで最後の攻撃を仕掛けるための体力を養う一分間の休息が、理保は待ち遠しくてたまらなかった。
そんな折、二人の距離が一時的に離れ、理保が小さくサイドステップを踏んだ時に、理保の視界に、ちらりとタイマーが映った。そこに表示されている数字は、第五ラウンドの残り秒数が二桁から一桁に移ったことを理保に伝えていた。
あと10秒で、この、つらかったラウンドが終わる。…… 理保はそれに安堵し、身体を寄せてきた夏美に向かって、クリンチに逃げるために両腕を伸ばした。
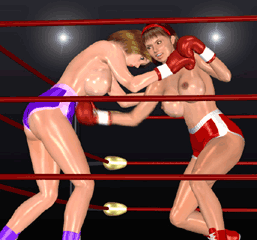
![]() その瞬間、夏美の上半身がわずかに沈み、身体の軸が右に傾いた。ラウンドの終了が近いことに気を取られ、一瞬だけ身体の力を抜いていた理保は、その動きに反応することが出来なかった。
その瞬間、夏美の上半身がわずかに沈み、身体の軸が右に傾いた。ラウンドの終了が近いことに気を取られ、一瞬だけ身体の力を抜いていた理保は、その動きに反応することが出来なかった。
理保が、「しまった!」 と感じる前に、夏美の右腕が斜め上に振り切られ、右拳を覆っている赤いグローブが、防御体勢の解けていた理保の柔らかいお腹に、深々と突き刺さった。

![]() ボクサーを志してからの激しい練習の中でさえも、一度も経験したようなボディブローの苦しみに、理保は両膝を折り、マウスピースを吐き出した。
ボクサーを志してからの激しい練習の中でさえも、一度も経験したようなボディブローの苦しみに、理保は両膝を折り、マウスピースを吐き出した。
「ダウン! ワン、…… トゥー、…… スリー、……」
キャンバスに突っ伏し、顔を苦痛に歪めている理保には、戦意、そしてファイトに必要な力が、体中の汗腺から流れ出ていくように感じられた。
それでも理保は、涎まみれの口から醜い呻き声を洩らしながら、己を必死に奮い立たせていた。
「あの日の麗子先生は、もっともっと苦しい思いをしたはず。…… こんなに簡単にKOされちゃったら、麗子先生に笑われちゃう。……」
理保はなんとか立ち上がり、レフェリーにファイティングポーズを向けた。そして、レフェリーがダウンカウントをエイトで止めると、第五ラウンド終了が鳴った。理保は、立ち上がるためにすべての力を使い果たしたかのように、思い足取りでロープを手繰りながら、金のコーナーへ戻っていった。
ようやく自分のコーナーに辿り着いた理保は、ストゥールに腰を落とし、ロープに両腕を伸ばした。何とか呼吸できるようになったものの、理保のお腹は、ボディブローのダメージでひくひくと不規則に波打っており、まだ満足に息を吸い込むことができる状態には戻っていなかった。

![]() 無防備な状態でボディに食らった一撃、…… そのせいで、この一分間で、最後の勝負を仕掛けるだけの体力を取り戻すというプランが崩壊してしまった。……
理保は、一瞬の油断を激しく悔いていた。
無防備な状態でボディに食らった一撃、…… そのせいで、この一分間で、最後の勝負を仕掛けるだけの体力を取り戻すというプランが崩壊してしまった。……
理保は、一瞬の油断を激しく悔いていた。
理保は、銀のコーナーに用意されたストゥールにどっかりと腰を下ろし、理保を見据えながら、大きく胸を張って、深呼吸を繰り返している夏美を、恨めしそうに見つめた。
「ポイントでは大きく差をつけられてるはずだから、判定になったらノーチャンス。勝つためには、夏美さんをキャンバスに沈めるしかない。……」

![]()
夏美をKOすることだけを考えて最終ラウンドに臨んだ理保だったが、直前のインターバルで充分に呼吸できなかったというツケはあまりにも大きく、最終第六ラウンドの残りが一分ほどになったときには、理保はすべての力を使い果たそうとしていた。
腕も満足に上がらなくなってきた理保の顔面に、夏美のパンチが雨のように降り注いだ。
平衡感覚を失い、大きく前によろめいた理保の顔を、夏美のショートフックが捻じ曲げた。その衝撃に、理保の股間から黄金色の液体が溢れ出た。

![]() 意識が飛びかけた理保は、本能的に夏美にクリンチすることで身体を支えようとした。しかし、夏美の身体に巻きつけられた理保の腕には力が入らず、理保の両脚も、一歩下がった夏美の動きに、まったくついていけなかった。
意識が飛びかけた理保は、本能的に夏美にクリンチすることで身体を支えようとした。しかし、夏美の身体に巻きつけられた理保の腕には力が入らず、理保の両脚も、一歩下がった夏美の動きに、まったくついていけなかった。
理保の腕が、汗に光る夏美の身体をずるずると滑り落ちていった。そして、理保の両膝が力なく折れ、キャンバスについた。
理保は、緩慢な動きで立ち上がり、カウントの進行を告げるレフェリーに身体を向けたが、理保の顔は、まだ失った表情を取り戻していなかった。そして、震える理保の両太腿を伝って、理保の黄金水が、キャンバスにぽたぽたとこぼれ落ちていた。

![]() 夏美は、惨めな姿を晒しながらも必死に試合続行を訴える理保の姿を、じっと見つめていた。
夏美は、惨めな姿を晒しながらも必死に試合続行を訴える理保の姿を、じっと見つめていた。
「理保さん、…… 理保さんは、アイドルなのに、…… どうしてそこまで。……」
やがて、レフェリーがカウントをエイトで止め、「まだできるか?」と理保に尋ねた。理保が鈍く反応し、小さく頷くと、レフェリーは二人に試合続行を命じた。
ニュートラルコーナーを離れた夏美の表情は、きっと引き締まっていた。
「理保さんは、アイドルとしてではなく、一人のボクサーとしてリングに上がってる。……
だから、理保さんを憐れんじゃいけない。…… 私は、自分の持つ最高のパンチを叩き込んで、理保さんにとどめを刺すことで、理保さんの頑張りに報いるべきなんだ。……」
夏美が、一旦理保の左側に回り込み、そこから素早く理保に近づいていくと、理保はぼんやりとした眼差しで夏美を追い、ふらついた足取りで、やっと夏美に身体を正対させた。
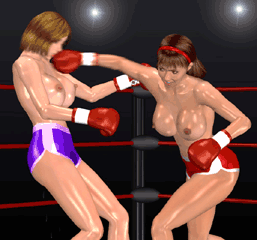
![]() 夏美が右腕を振りかぶり、理保に向かって大きく踏み込むと、理保はその動きにわずかに反応したが、夏美はそれに構わず、力一杯右腕を振り切った。
夏美が右腕を振りかぶり、理保に向かって大きく踏み込むと、理保はその動きにわずかに反応したが、夏美はそれに構わず、力一杯右腕を振り切った。
「愛のお注射っ!!」
夏美の右拳を覆っている赤いグローブが、理保の下アゴにめり込んだ。そして、次の瞬間には、理保の身体は真後ろに吹き飛んでいた。
「ダウン! …… ワン、…… トゥー、…… スリー、…… フォー、……」
だらしなく股を開き、大の字に伸びたまま動かなくなった理保に向かって、レフェリーがダウンカウントをスタートさせた。
自分がこの試合三度目のダウンを喫し、目の前でカウントが進められている気配を、かすかに感じ取った理保は、何とか立ち上がろうとした。しかし、理保には、腕や脚はおろか、グローブの中に収められている指一本でさえ、動かす力は残っていなかった。

![]() 「…… ああ、…… 私、もう立てないのかな。……」
「…… ああ、…… 私、もう立てないのかな。……」
そんな思いが理保の脳裏をかすめると、キャンバスに横たわることの心地良さが、理保の全身を優しく包み込んだ。そして、その心地良さは、理保がやっとのことで繋ぎ止めていた意識の糸の最後の一本を、静かに断ち切った。
「…… ナイン、…… テン! ノックアウト!!」
レフェリーが、眠るように横たわる理保に最後の数カウントをコールし、頭の上で両腕を交差させると、試合終了を告げるゴングが打ち鳴らされた。
勝者のコールを受け、レフェリーに右腕を掲げられている間も、夏美は、ぴくりとも動かない理保に、心配そうな眼差しを向けていた。そして、勝利のセレモニーが終わると、夏美は、すぐに理保を取り囲んでいる数人の輪に加わり、理保のそばに両膝をついて、理保の顔をじっと見つめ、理保の意識が戻るのを待った。
やがて、理保の顔に表情が戻り、薄目になっていた眼もしっかり開いた。理保の瞳は、自分を取り囲んでいる何人かの顔を巡ったあと、安堵のため息を洩らした夏美のところで止まった。
「…… 負けちゃいました。…… 夏美さん、…… 強いですね。……」
途切れがちな理保の言葉に、夏美は小さく首を横に振った。
「…… 私、…… もっともっと練習して、…… 夏美さんのように強くなります。……
だから、必ず、…… もう一度試合してくださいね。……」
今度は首を縦に振った夏美の眼に、涙がじんわりと溢れてきた。理保のボクシングに対するひたむきな姿勢に、その理保と巡り会い、デビュー戦のリングの上で試合を行えたことに、夏美は深く感激していた。
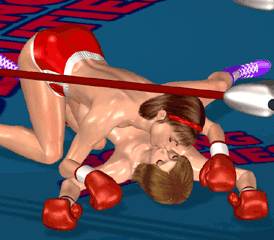
![]() 夏美が、はぁはぁと少し弱々しい呼吸を続けている理保に覆い被さるようにして、すっと自分の顔を近づけると、理保は小さく微笑んだ。
夏美が、はぁはぁと少し弱々しい呼吸を続けている理保に覆い被さるようにして、すっと自分の顔を近づけると、理保は小さく微笑んだ。
理保の顔を間近で見つめた夏美は、ゆっくり自分の唇を理保の唇に寄せた。すると、理保は一瞬だけ嬉しそうな表情を見せ、静かに目を閉じた。
「愛のお注射っ。……」
夏美も静かに眼を閉じ、そのまま理保の唇を優しく覆った。
試合後、リングドクターから、「問題なし」の診断が出たものの、理保は、より精密な検査を受け、また、充分な休養を取るための環境を整えるということもあり、大事を取って二、三日入院することになった。
翌日、理保が居心地のいい個室で、ベッドに横たわって雑誌を読んでいたとき、ドアが小さくノックされた。理保が、「はい、どうぞ。」と返事をすると、病室のドアが開き、歳の割には若造りな感じの衣装を着た、一人の中年男性が中に入ってきた。
「あ、社長。……」
「理保ちゃん、身体の具合はどう?」
理保に、『社長』 と呼ばれたその男性は、持参した花を花瓶にセットすると、ベッドのそばにあった椅子を引き寄せて、その上に腰を下ろした。
「あ、はい。もう大丈夫です。…… ご心配をおかけしました。」
「そう。それはなによりだね。…… 試合の結果は、玉砕、って感じだったけど、本当に素晴らしいファイトだったよ。……
正直、私は理保ちゃんがあそこまでやれるとは思ってなかった。」
「…… ありがとうございます。…… でも、負けは負け。…… それに、あんな無様な姿を晒したんじゃ、お仕事、減っちゃいそうですね。……
本当に、…… 申し訳ありません。……」
「…… それがさぁ、理保ちゃん。……」
その男性は、そこで一旦言葉を切り、自分の座っている椅子を、理保のベッドに近づけた。
「…… まったく逆なんだよね。試合のあと、事務所の電話は鳴りっ放しだよ。ファンからのメッセージがほとんどだけど、新しい契約の話も結構多い。BBIの日本事務局から、イメージファイターとして理保ちゃんを使いたいって話も来てるよ。理保ちゃんの頑張りを、業界は放っておかなかった、ってことだね。……
あんまり電話が多いもんだから、石川君に、『お前、理保ちゃんのマネージャーなんだから、ちゃんと仕事の段取り組んどけよ。』って言って、事務所から逃げてきちゃった。」
社長は、そう言うと、さも嬉しそうに、「あっはっはっは」 と声を上げて笑った。
「…… だからね、仕事のことは、何も心配しなくていいんだよ、理保ちゃん。事務所としても、プロボクサー・双葉理保を、全力で応援するつもりでいる。理保ちゃんが強いプロボクサーになることを望むなら、事務所でできるだけのことは、何でもしてあげる。約束するよ。」
社長の顔は、優しい微笑みに満ちていた。理保は恐縮したような照れ笑いを返し、小さく頭を下げた。