

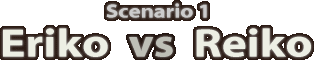
お気に入りの、少し青味がかったダークグリーンのトランクス、同じカラーコンビネーションのシューズを身につけた挑戦者は、胸を張り、まっすぐに前を見据えて、リングへと続く通路をゆっくりと歩いていった。
その挑戦者は、リング上へのステップの手前で立ち止まった。彼女はその場でしばし頭を垂れ、この試合で、自分自身に課した約束事を心の中で復唱した。そして、再び視線をリング上に向けると、軽い足取りでステップを登り切った。
彼女がロープをくぐるために身を屈めようとしたとき、銀のコーナー近くのリングサイド席から声が掛かった。
「麗子先生、頑張って!!」
『麗子先生』と呼ばれたその挑戦者は、声の主の方に顔を向け、にっこりと微笑んだ。そして、すぐに声の主から視線を切り、赤いロープの下二本を跨ぐようにして、ロープの内側へと身を滑り込ませた。
三月初旬にしては、とても暖かい日差しが関東地方に降り注いだ日の夜、BBI極東地区フェザー級タイトルマッチの会場となったY市体育館は、すでに大勢の観衆で埋まり、熱気に包まれていた。
日本、そして東アジア全域をカバーするBBI極東地区チャンピオンの白鳥絵里子は、現役の人気レースクイーンという異色の経歴ながら、デビュー以来圧倒的な強さで連勝を重ね、あっという間にBBIの日本タイトルを手に入れた。そして、一年ほど前、BBI極東地区のタイトルをほぼ独占するほど強豪がひしめくK国に乗り込み、地元K国人の極東地区フェザー級チャンピオンに挑戦した絵里子は、敵地であることをまったく問題にせず、チャンピオンをわずか二ラウンドで完全に粉砕し、あっさりと東アジアの頂点に立った。
圧倒的な強さ、…… 絵里子の戦績が、如実にそれを物語っていた。絵里子の対戦相手で、第六ラウンド開始のゴングを聞いたものは過去に一人だけしか居らず、その選手でさえも、その約二分後にはキャンバスの上で完全に意識を失い、そのまま病院直行の憂き目を見ていた。18戦18勝18KO。絵里子の戦績は、塵一つない完璧なものだった。
この夜の麗子との対戦で、極東地区タイトルの四度目の防衛戦を迎える絵里子は、試合前、「この試合に勝ったら、日本タイトル、極東地区タイトルを返上し、最も選手層の厚いアメリカに活動の拠点を移して、世界タイトルのみを追う。」と宣言していた。
挑戦者となる水咲麗子も、元高校の数学教師という、BBIに籍を置くボクサーとしては極めて稀な経歴を持っていた。
デビュー当時、麗子は、高校教師とプロボクサーの二足の草鞋を履き、学校が、夏休み、冬休みに当たる時期に行われる興行にのみリングに上がっていた。しかし、絵里子が日本タイトルを手にしたのと同時期に当たる二年ほど前に教職を辞し、以来、積極的に試合をこなすようになった。
元教師らしい極めてオーソドックスなボクシングスタイルで着実に勝ちを積み重ねた麗子は、三ヶ月ほど前に行われた絵里子への指名挑戦権を賭けた試合で、日本ランク一位の選手を最終ラウンドでキャンバスに沈め、ついにトップコンテンダーの地位にまで上り詰めた。そして、最新の極東地区ランキングでも三位となり、日本タイトルのみならず、絵里子が併せ持つ極東地区タイトルの挑戦者に認定され、この夜を迎えた。
巨乳がウリの人気アイドル、双葉理保は、普段からスポーツジムでボクシングエクササイズを行ったり、イメージビデオにその映像を取り入れたりするほどのボクシング好きで知られていたが、その背景には、麗子の存在が深くかかわっていた。
理保が三年間の高校生活を送った学校に、麗子は数学の教師として赴任しており、理保は麗子から直接数学の授業を受けていた。そして、理保が高校二年の夏休みに、麗子はプロボクサーとして、初めてBBIのリングに上がった。情熱的な教師として麗子を尊敬していた理保は、チケットを購入して会場に足を運び、麗子のデビュー戦を生で観戦した。
リングの上で闘う麗子の姿に、そして、デビュー戦をKO勝利で飾り、レフェリーに右手を高く掲げられ勝者のポーズを取る麗子の姿に強い衝撃を受けた理保は、「私もいつか、麗子先生と同じように、プロボクサーとして、このリングの上で闘いたい」という想いを、密かに抱くようになった。以来、熱狂的な麗子のファンとなった理保は、麗子と、先生と生徒以上のつながりを持つようになり、ある意味、嗜好や趣味の域を超えて、ボクシングにのめり込むようになっていった。
高校を卒業し、高校時代から続けていたアイドル業に専念するようになってからも、理保は、でき得る限り、麗子の試合を観戦した。そして、麗子にとって大一番となるこの夜も、理保は銀のコーナー近くのリングサイド席を確保し、忙しい仕事の合間を縫って、麗子の応援に駆けつけていた。
日本ランカー同士の対戦となったセミファイナルで、地元出身の選手が格上の相手を食ったことで、会場内はやや興奮状態のまま、メインイベント前の休憩に入っていた。そして、そのころ、理保は、麗子の控室に姿を現していた。
すでにリングコスチューム姿になった麗子が、いよいよ赤いグローブに拳を通そうかという頃、麗子と談笑していた理保が、何の気なしに、「今日の相手は今までとは比べ物にならない強敵ですね。」
というようなことを口にすると、麗子は、理保に向けていた視線を床に落とし、自嘲気味に笑った。
「実はねぇ、…… 今日の相手、BBIの、日本、そして極東地区フェザー級チャンピオン、白鳥絵里子も、……
あなたと同じ、私の教え子の一人なの。」
「えっ? そ、それ、本当ですか?」
麗子は、驚きの声を上げて自分を見つめている理保の顔から視線を外し、「まぁ、教え子、って言えるかどうかは、よくわからないけどね、……」と呟き、やや表情を崩して小さく息を吐き出した。
「…… 私があなたの通った高校に赴任する前、三ヶ月だけ、あるお嬢様学校で代任教師をしたことがあって、……
そのとき、白鳥さんはそこの三年生だったの。……」
「そうだったんですか。……」
「…… 本当に目立つ子だったわ。…… 全教科を通じて成績優秀、もちろんこの世界で日本一になるくらいだから、運動神経も半端じゃなかった。おまけに容姿端麗、お家はお金持ち。……
とにかく、欲しいものは何でも手に入る子だったのね。…… でも、あまりにも環境に恵まれた分、心だけがなかなか成熟していかない。……
担任の先生がそう言っていたし、私も似たような印象を持ってたわ。…… この子、このまま社会に出たら、どうなっちゃうのかなぁ、って。当時は、ちょっと心配したりもしてたのよ。」
麗子がそこまで話し終わったとき、麗子のグローブのテーピングが終わった。麗子は、グローブの感触を確かめるように、何度か両拳を付き合わせると、理保に向かってにっこり微笑んだ。
「それじゃ、試合に集中するから、お話はこれぐらいにしましょう。応援よろしくね。」
「あ、はい。…… 一生懸命応援します。…… 先生、頑張ってくださいね。」
理保の激励に麗子が頷くと、理保は宛がわれたいた椅子から立ち上がり、麗子に向かって深く一礼してから麗子の控室を後にした。

![]() 絵里子が赤いロープをくぐると、観客席から大きな歓声が上がった。リングインした絵里子は、黒いグローブに包まれた右の拳を突き上げ、その力を鼓舞するポーズを見せつけて、リングの中を一周した。
絵里子が赤いロープをくぐると、観客席から大きな歓声が上がった。リングインした絵里子は、黒いグローブに包まれた右の拳を突き上げ、その力を鼓舞するポーズを見せつけて、リングの中を一周した。
銀色のコーナーマットを背にした麗子は、銀色のコーナーマットに背中を凭れかけ、「あの子らしいリングパフォーマンスね。」と思いながら、絵里子がリング内をねり歩く様子を眺めていた。

![]() レフェリーに呼ばれてそれぞれのコーナーを離れた二人は、リングの中央で対峙し、しばらく試合前の注意に耳を傾けていたが、レフェリーの話が終わっても、絵里子はコーナーに戻ろうとせず、相変わらず見下すような視線を麗子に向けたまま、口を開いた。
レフェリーに呼ばれてそれぞれのコーナーを離れた二人は、リングの中央で対峙し、しばらく試合前の注意に耳を傾けていたが、レフェリーの話が終わっても、絵里子はコーナーに戻ろうとせず、相変わらず見下すような視線を麗子に向けたまま、口を開いた。
「麗子先生、…… わたくしのこと、覚えていらっしゃいますか?」
麗子はわずかに口元を引き上げ、小さく頷いた。
「もちろん覚えていますよ、白鳥さん。…… あの頃に比べると、随分逞しくなられましたね。……」
麗子がそう答えると、絵里子の口元にもわずかに笑みが浮かんだ。
「ありがとうございます。…… 高校時代、短い間ではありましたが、わたくし、麗子先生からとても多くのことを学ばせていただきました。……
先生にはいつかご恩返しをしなければと思っているのですが、…… でも、このリングの上では実力がすべて。……
たとえ相手が麗子先生であっても、情け容赦はいたしませんわ。よろしいですね。」
絵里子の言葉に、麗子が再び小さく頷くと、絵里子の瞳が一瞬妖しく輝いた。そして絵里子は麗子から視線を切り、ゆっくりと振り向いて、金色のコーナーへと戻っていった。
それを見届けた麗子も、銀のコーナーへと身体を向け、ゆっくり歩き出した。わずかに俯いた麗子は、「あの子、本当に変わらないわね。」と呟き、クスリと小さく笑った。
理保は、過去に何度も、リングサイド席から麗子の勝利を信じて麗子の試合を観戦してきた。その中には、多少相手が格上と見られていた試合もあったが、試合前、試合中を通して、必ず麗子が勝利するという理保の信念が揺らぐことはなかったし、事実、麗子が敗者として試合を終えたことは、これまでに一度もなかった。
しかし、この、絵里子との試合だけは、理保の心中は穏やかではなかった。「今夜、私は、キャンバスに横たわって試合終了のゴングを聞く麗子先生を目撃することになるのかも知れない。……」試合前、理保は、その予感を拭うことができずにいた。
いよいよ二人がそれぞれのコーナーに戻り、BBIの係員からマウスピースを受け取ると、試合開始のゴングが鳴った。理保の祈るような眼差しの前で、麗子と、『最強の教え子』との一戦の幕は、切って落とされた。

![]() 第一ラウンド、麗子は長いリーチを活かして、鋭いジャブを絵里子の顔面に飛ばし続け、破壊的な強打を誇る絵里子に、接近戦を許さなかった。
第一ラウンド、麗子は長いリーチを活かして、鋭いジャブを絵里子の顔面に飛ばし続け、破壊的な強打を誇る絵里子に、接近戦を許さなかった。
一試合前の、麗子が絵里子への指名挑戦権を勝ち取った試合で、理保は、麗子の動きがそれ以前の試合よりも格段に良かったと感じていたが、この絵里子との試合では、更に数段上のパフォーマンスを披露しているように思えた。
理保は、試合前、もし麗子が絵里子を破るチャンスがあるとすれば、それには試合が長引くことが絶対条件だと考えていた。
絵里子は過去の試合で、ことごとく早いラウンドのKO勝ちを収めている。それは素晴らしいことだが、反面、長いラウンドの試合を経験したことがない、ということでもある。もし、このまま、麗子が絵里子の強打をシャットアウトしたままで試合が終盤までもつれれば、絵里子がスタミナ切れを起こすかも知れない。……
第二ラウンドに入っても、麗子のスピード、ジャブの切れは変わることなく、麗子は相変わらず、絵里子の攻撃を未然に防ぐことに成功していた。理保には、絵里子がまだ様子見をしているようにも見えたが、それでもこのまま試合が進めば、麗子が絵里子を破って、東アジアの頂点に立つ可能性は充分ある、と、理保は期待に胸を膨らませた。
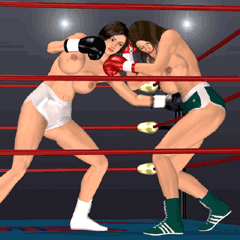
![]() しかし、第三ラウンドに入ると状況は少し変わってきた。
しかし、第三ラウンドに入ると状況は少し変わってきた。
アクセルを吹かし始めた絵里子が、不規則な動きで何度となく麗子のジャブの網を破り、至近距離から麗子に強烈なパンチを浴びせるようになってきた。
顔面への致命的な一撃だけはきっちり回避しているものの、重いボディブローを次々と叩き込まれると、麗子の動きは、徐々にその輝きを失っていった。
試合は、絵里子にとって未知のラウンド、そして、理保が、『ここまで試合が続けば、麗子にチャンスが生まれる』と考えていた、第七ラウンドに入っていた。
麗子の身体に絵里子の拳が打ち込まれるたびに、理保は、自分の考えがあまりにも甘いものであったことを思い知らされていた。第七ラウンドに入っても、絵里子はまったく疲れを見せる様子もなく、衰弱の度合いを濃くしていくのは一方的に麗子の方だけだった。
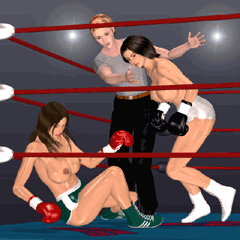
![]() 第七ラウンドが残り四十秒ほどになったとき、脇腹にボディフックを食らい、左腕のガードがわずかに下がった麗子の顔面を、絵里子の右フックが捕らえた。麗子は、膝を踏ん張ったままその衝撃に耐えることができず、キャンバスにどすんと腰を落とした。
第七ラウンドが残り四十秒ほどになったとき、脇腹にボディフックを食らい、左腕のガードがわずかに下がった麗子の顔面を、絵里子の右フックが捕らえた。麗子は、膝を踏ん張ったままその衝撃に耐えることができず、キャンバスにどすんと腰を落とした。
麗子がキャリア十七戦目にして初めて喫するダウン、そして、それは、理保が初めて目撃する、『麗子がリングの上で相手に殴り倒されたシーン』
だった。
麗子がカウント8で立ち上がり、試合が再開された。麗子は、防戦一方になりながらも、残り数十秒を、何とかダウンせずに凌ぎ、第七ラウンドを終えた。

![]() 続く第八ラウンドも、生命線であるはずの、ジャブの鋭さ、フットワークの軽快さを完全に失った麗子は、一方的に絵里子の攻撃の前に晒された。
続く第八ラウンドも、生命線であるはずの、ジャブの鋭さ、フットワークの軽快さを完全に失った麗子は、一方的に絵里子の攻撃の前に晒された。
ほとんど自分から手を出せなくなるほどまでに衰弱した麗子のボディへ、顔面へ、絵里子の強烈なパンチが突き刺さり、麗子の端正な顔立ちが何度も歪んだ。それでも麗子は、驚異的なタフネスで、第八ラウンドの三分間を、ダウンすることなく耐え切った。
第九ラウンドも、麗子がひたすら絵里子の攻撃を浴びるだけの展開だった。
ラウンドの半ばには、麗子がついにこの試合二度目のダウン、さらにラウンド終了間際、麗子は再び、崩れ落ちるように両膝を折った。
 「ダウン。…… ワン、…… トゥー、…… スリー、……」
「ダウン。…… ワン、…… トゥー、…… スリー、……」![]()
レフェリーの指示に従ってニュートラルコーナーで待機している絵里子は、背中を黒いコーナーマットに凭れかけ、この試合、三度目のダウンカウントを受け取る麗子を、悠然と見下ろしていた。
「…… もういい。…… もう立たなくていいよ、麗子先生。…… もう充分だよ。……」
すでに、理保の心の中は、とにかく一刻も早く試合が終わって欲しい、麗子が殴られる光景を、これ以上見たくないという気持ちで一杯になっていた。
そんな理保の願いを否定するように、麗子は、ややふらつきながらカウント8で立ち上がり、レフェリーに力のないファイティングポーズを向けた。
ほどなく第九ラウンド終了のゴングが鳴り、二人は、それぞれのコーナーに引き上げてきた。
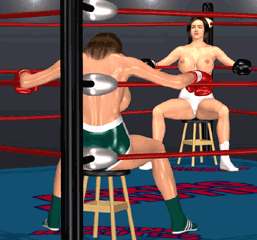
![]() 最終ラウンド前の、一分間の休息時間を過ごす二人の様子はあまりにも対照的だった。
最終ラウンド前の、一分間の休息時間を過ごす二人の様子はあまりにも対照的だった。
金のコーナーのストゥールに腰を下ろした絵里子は、きっちり胸を張り、大きく深呼吸を繰り返しながら、対角線上のコーナーの麗子をしっかりと見据えていた。逆に、下を向いて大きく口を開け、はあはあと荒い呼吸を繰り返す麗子の背中は、痛々しいほどに丸まってしまっていた。
最終第十ラウンド、麗子は、インターバルの間に回復した、わずかばかりの体力を費やして反撃を試みたが、それもほんのわずかの時間だった。絵里子の圧倒的な力の前に、麗子はずるずると後退を始め、やがて銀のコーナーに追い詰められた。

![]() ようやく顔を覆う位置に両拳のグローブを上げている麗子に向かって、絵里子は、渾身の力を込めて、右腕を振り切った。
ようやく顔を覆う位置に両拳のグローブを上げている麗子に向かって、絵里子は、渾身の力を込めて、右腕を振り切った。
「百花繚乱っ!」
黒いグローブが麗子のお腹に深々とめりこむと、麗子の口から、普段の優美な立ち振る舞いからは想像もつかないような醜い呻き声が洩れた。

![]() 絵里子が口元にわずかな笑みを浮かべて一歩退くのと同時に、麗子は、涎まみれのマウスピースを吐き出し、キャンバスに転がった。
絵里子が口元にわずかな笑みを浮かべて一歩退くのと同時に、麗子は、涎まみれのマウスピースを吐き出し、キャンバスに転がった。
「ダウン。…… ワン、…… トゥー、…… スリー、……」
顔一杯に苦悶の表情を溢れさせ、片腕でお腹を抑えてキャンバスをのたうつ麗子に、レフェリーは、この夜、四度目のダウンカウントを向けた。
それでも麗子は、カウントアウト寸前で立ち上がり、両腕を胸の前に構えた。しかし、麗子の両脚は、あまりの苦しみにぶるぶると震えており、麗子のお腹も、呼吸が完全に戻っていないことを示すように、まだ不規則に動いていた。

![]() カウントをナインで止めたレフェリーは、麗子の試合続行の意思を確認すると、キャンバスに落ちていた麗子のマウスピースを拾い、BBIのスタッフに手渡した。
カウントをナインで止めたレフェリーは、麗子の試合続行の意思を確認すると、キャンバスに落ちていた麗子のマウスピースを拾い、BBIのスタッフに手渡した。
やがて、軽く水で濯がれたマウスピースが麗子の目の前に差し出された。麗子が、唇を小刻みに震えさせながら小さく口を開け、再びマウスピースを咥え込むと、レフェリーは試合再開を命じた。
絵里子は、口元にうっすらと不敵な笑みを浮かべ、背にしていたニュートラルコーナーを離れた。
その場から一歩も動けない麗子に、絵里子が二度三度とパンチを浴びせると、麗子は絵里子にしがみついてきた。

![]() すると、自分の胸に押し当てられた麗子の頭を軽く抱え込んだ絵里子が、いかにも苦しそうに不規則な呼吸を繰り返す麗子の耳元で囁いた。
すると、自分の胸に押し当てられた麗子の頭を軽く抱え込んだ絵里子が、いかにも苦しそうに不規則な呼吸を繰り返す麗子の耳元で囁いた。
「…… さすがは麗子先生、その往生際の悪さ、本当に大したものですわ。……
でも、もう立っているだけでも、たまらなくお辛いでしょう? …… 最後のご恩返しに、すぐに楽にして差し上げますわ。……
今までありがとうございました、麗子先生。……」
そして、絵里子が軽く身体を捩り、麗子の肩をグローブで突き放すと、麗子は、銀色のコーナーマットに向かって、よたよたと後ずさりした。
絵里子が再び自分との距離を詰めてきても、麗子にはもう、顔をガードする位置にまで腕を上げる力は残っていなかった。そして、絵里子が、麗子のアゴに振りの小さいアッパーを続けざまに叩き込むと、麗子の腰が落ち、中途半端に上がっていた両腕からも、力が抜け落ちてしまった。
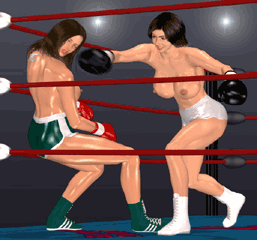
![]()
「真・百花繚乱っ!!!」
全体重をかけてスイングした絵里子の右拳の黒いグローブが、麗子の顔面にめり込んだ。麗子の口から白いマウスピースが吹き飛び、それはリングの外でワンバウンドして、心配顔で試合を見守る理保の足元に転がった。
「いやぁぁぁっ!!」
理保は悲鳴を上げ、顔を両手で覆った。
「ダウン。…… ワン、…… トゥー、…… スリー、…… フォー、……」

![]() 場内にダウンカウントのアナウンスが流れると、理保は顔を覆っていた手を下ろし、リングの上に視線を戻した。そこには、キャンバスに四肢を投げ出し、大の字に伸びた麗子と、ニュートラルコーナーに控えて、麗子を見下ろしている絵里子の姿があった。
場内にダウンカウントのアナウンスが流れると、理保は顔を覆っていた手を下ろし、リングの上に視線を戻した。そこには、キャンバスに四肢を投げ出し、大の字に伸びた麗子と、ニュートラルコーナーに控えて、麗子を見下ろしている絵里子の姿があった。
カウントが後半に入っても、麗子の身体は、ときおり、ぴくんぴくんと震えるだけで、麗子の意思通りに動く気配はまったくなかった。
「…… エイト、…… ナイン、…… テン! ノックアウト!!」
レフェリーが頭上で両腕を交差させると、試合終了を告げるゴングが連打された。麗子の、最強の教え子への挑戦は、失神KO負けという形で幕を閉じた。
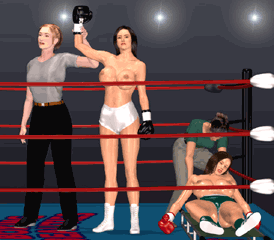
![]() しばらくたってから、麗子は意識を取り戻したものの、すべての体力を使い果たし、破壊しつくされた麗子は、まったく自力で動くことができなかった。
しばらくたってから、麗子は意識を取り戻したものの、すべての体力を使い果たし、破壊しつくされた麗子は、まったく自力で動くことができなかった。
レフェリーに右手を掲げられ、勝者のポーズをカメラマン席に向けた絵里子に、たくさんのカメラのフラッシュがたかれる傍らで、麗子はBBIのスタッフの手によって担架に載せられ、そのままリングから運び出された。
その後、予告どおりに、リングの上で極東地区、および日本タイトルの返上と、アメリカに拠点を移して活動をするために、しばらく日本国内での試合をしないことを発表した絵里子は、試合前にコミッショナーに返還したチャンピオンベルトを受け取ることなく、リングを後にした。
試合後のセレモニーが終わり、絵里子の強さを堪能した観客が会場の出口へ流れ始めた頃、理保は沈痛な面持ちでシートから腰を上げ、麗子の控室へと向かったが、病院直行となった麗子に会うことはできなかった。
スタッフから、『お医者さんから許しが出たら必ず連絡するから、面会はそれまで待ってちょうだい』
という麗子からのメッセージを受け取った理保は、重苦しい表情のまま、家路についた。
麗子が絵里子の前に玉砕した二日後、「麗子との面会がOKになった」との連絡を受けた理保は、さっそく麗子が入院している病院に向かった。そして、麗子の具合について、担当の医師から、「心配しなくても大丈夫だ」という返事をもらい、理保はほっと胸を撫で下ろした。
その後、理保は、しばらくの間、麗子とのおしゃべりに興じた。やがて麗子は、絵里子との試合に至るまで、自分がどんな思いでボクシングを続けてきたのかを語り始めた。
ボクシングに興味を持ち、自分なりに研究していくうちに、自分の理論が正しいかどうかを、どうしても真剣勝負の場で確かめたくなって、リングに上がる決意をしたこと。絵里子の試合を観戦した際に、絵里子のボクシングに、自分の『ボクシングの理想像』を垣間見たこと。絵里子が日本チャンピオンとなったことで、絵里子と試合をするためには、自分がそれにふさわしい挑戦者にならねばならないと感じたこと。そして、絵里子と試合をすることで、自分のボクシングに対する考え方が合っているのか間違っているのか、すべての答えが出る、と確信したこと。……
麗子が、絵里子との試合を最後に引退するつもりだったと聞いて、理保は少し驚いた。「負けたから引退するんじゃない。これまでに培ってきた自分のボクシングを、すべて絵里子にぶつけることで、ボクサー生活を完結させ、また数学の先生に戻る。そういう思いで、この二年間を過ごしてきた。」
と、麗子は理保に話した。
麗子は、「だから、一分一秒でも長く、試合を続けたかった。どんなに辛くても、たとえ反撃する力はもう残っていないと感じたとしても、立ち上がれるなら立ち上がる。何度ダウンをしても、絶対に自分からは試合を投げない。そう自分に言い聞かせてからリングに上がった。」
とも語った。ああ、そういうことだったのか、ボロボロに打ちのめされ、何度キャンバスに這わされても、その度に麗子が立ち上がり、試合を続けたのはそういう理由だったのか、と理保は思った。
ボクシング人生を振り返る麗子の、満足感に満ちた穏やかな笑顔は、理保の中でくすぶっていた『私もボクサーとしてリングに上がりたい』という気持ちに火をつけ、それは徐々に大きくなってきていた。
「ねぇ、先生。…… 先生は、プロとして試合をしたいと思ったとき、あまり悩まずに、すっと決断できたんですか?」
理保が何の気なしにそう尋ねると、麗子は少しだけ表情を崩した。
「そりゃぁねぇ、…… 大勢の人たちの前で、女性同士が殴り合うわけだから、もちろんすごく悩んだわよ。周りに反対されるのだってわかってたし。……
でね、私の恩師に当たる、ある人に相談してみた。…… そしたら、その先生は、『本当に自分がやりたいと思ったことを、手を出さずに見送ってしまったという後悔は、一生残るものです。あなたはまだ若い。いろんなことにチャレンジできるのは、若いうちだけですよ、麗子さん。』
って言ってくれたの。……」
やりたいことをしなかったという後悔は、一生残る。…… その言葉に、理保の心は大きく揺れた。
「…… そのあと、もう一度よく考えた。…… それで、ボクシングを真剣勝負という形で実体験できるのは、身体が動く若いうちだけ。先生の仕事や、数学の研究は、若さを失ってからでも、いくらでも続けることができるじゃないか、っていう結論に辿りついたの。……
それなら答えは一つしかない。決断するなら今だ、って。」
麗子とのおしゃべりは、その後もしばらく続いたが、理保は、その間も、麗子がリングデビューを決めた経緯を噛み締めていた。
…… 私も同じ。…… リングの上で闘いたいなら、今決断すべきではないだろうか。……
その翌日、理保は、所属事務所の社長に、「プロボクサーとして、BBIのリングの上で闘いたい。」 と打ち明けた。
「理保ちゃんは、本当に情熱的な子だからねぇ、……」
理保の意思を受け止めた社長は、固くしていた表情を崩し、ニヤリと笑った。
「…… いつかそんなことを言い出すんじゃないか、って思ってたんだよね。」
麗子の最後の試合から二週間ほどが経ったある日、事務所のHPに、理保がBBIの選手登録申請を行い、審査をパスしたとの記事が掲載された。『巨乳アイドル双葉理保がプロボクサーへ』
のニュースに、アイドル界に大きな衝撃が走った。